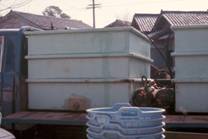|
漁業技術の画像集・FishTech
著作者/水産大学校名誉教授・理学博士 前田弘
Back to: Top Page |
FishTech 目次 | ご覧のページ
|
|
第 4 部 50 その他 14 各地の魚市場 14-13 枕崎等 生産地の魚市場をどの程度まで機械化することが可能であり、一般の社会の近代化に対応できるかが問題になる。 魚市場における水揚げ装置の機械化には問題が多い。一本釣・刺網・底曳網のように多種多様の魚種が揚げられ、 しかもそれらが活魚か鮮魚として消費される場合、漁獲物は船上において魚種と大きさによって分けられ、凍結されて いるか、十分氷を入れて、そのまま競にかけられる準備ができた状態で揚げられるので、選別に関する問題はない。 機械化による魚の傷みや各魚種にどう対応するかが問題となる。欧米において漁獲物処理の機械化が進んでいるのは、 魚種が限られしかも、大部分はフィレーの形で店頭に並べることを目的とするという利点がある。 日本では、選別が問題になるのは、巻き網による漁獲物である。漁網から漁船に、漁船から陸上に魚を移す フイッシポンプの導入においてさえ問題になった。これは、大部分が養殖の餌となり、魚の傷みは問題にならない ことは予想できても、競落とされるまでは、一部生鮮食品として消費される可能性が残っているためである。 漁獲物が傷むことを問題にするならば、エビトロール船の船上におけるサイズ選別機(グレーダと呼ばれる)では、 この問題はなく、実用化している例である。
 [No.1: ft_image_50_14m/image001.jpg]
漁獲物はそのまま魚艙に取込むので、選別されていない。この写真に写っているように上縁に太い鉄の輪のついた タモ網で掬われ、運搬船のデリックを操作し、陸上のホッパに空けられる。この作業は普通は3人で行われる。 ホッパに落された魚は陸上の作業員によって行われる。魚艙容積が150トンとすれば、かなり時間がかかる。
 [No.2: ft_image_50_14m/image003.jpg]
No.3
No.4
No.5
 [No.6: ft_image_50_14m/image013.jpg]
No.7
No.8
No.9
 [No.10: ft_image_50_14m/image019.jpg]
No.11
No.12
No.12はそのためのトラックを示す。他のリフトやトラックで運ばれた角氷は、この装置で運上げられ、砕かれて 運搬船に積込まれる。 巻き網の運搬船は、沖で漁獲物を積込むと最寄りの港で揚げ、翌日の夕方までに船団に帰り、次の操業に待機し なければならない。そのために漁獲物の水揚げと氷の積込みの時間短縮は大切である。
 [No.13: ft_image_50_14m/image025.jpg]
これらの写真の他にファイル「カツオ竿釣」に示したように、遠洋で漁獲された冷凍カツオも揚げられる。
 [No.14: ft_image_50_14m/image027.jpg]
大阪湾南部 都市圏内において底曳網漁業を行う漁協が現代社会に適応する方法の一つは活魚の供給である。その例を示す。 この漁協における漁船と漁法はファイル「大阪湾南部の底曳網漁船」に示した。
 [No.1: ft_image_50_14m/image029.jpg]
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.3は魚を販売する薄箱と活きた魚を入れる袋である。 No.4は競場である。競人も仲買人も共に女性ばかりである。 競落された活魚は活魚トラックで運ばれる。その他に漁協の近くの陸上に水槽をおいて、そこで売られる。 日 生 日生は岡山県の東端にあり、枡網の発祥の地として知られている。内海としては例外的なサワラ流し網と板曳網が ある。底曳網漁業が盛んである。その漁業はファイル「日生における底曳網漁船」に記した。 ここでは瀬戸内海の一般的な魚市場の例として上げる。
 [No.1: ft_image_50_14m/image041.jpg]
|
 [No.2: ft_image_50_14m/image043.jpg]
No.3
No.4
 [No.5: ft_image_50_14m/image051.jpg]
No.6
No.7
これらの写真を詳細に見ると数種類の箱が見られる。同じ漁法による漁獲物か同じ目的で消費されるものを同じ 種類の箱に詰める(並べる)とすれば、漁獲物の多様性が想像される。 普通、魚を箱に並べるとき、縁を上にし、底に魚を並べる。しかし、ここではソバの皿のように底はスノコになり、 底を上にして魚を並べる。ソバの盛り方のように並べると思えばよい。 鞆の浦
 [No.1: ft_image_50_14m/image055.jpg]
No.2
No.3
大分近郊
 [No.1: ft_image_50_14m/image061.jpg]
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
 [No.8: ft_image_50_14m/image075.jpg]
No.9
競が終わるとNo.9に示すように頭に手鈎を打ち込んで絞められる。 一本釣で漁獲されたここのアジは、関アジとして有名である。首を折って絞められる。魚を絞めて鮮度を保持する 技術(魚は苦しませると味が落ちる。魚をすぐに殺すことを魚を絞めるという)は、氷が一般でなかった時代から 使われている日本における伝統的な技術である。全国各地で一本釣の漁獲物ばかりでなく、養殖されたタイやブリも 絞められる。この場合手鈎を使う方法と氷で十分冷やした海水に魚を入れて絞める方法がある。手鈎によって絞める 方法は広く使われるが、地方によっては、絞めた人によって魚の値段が異なることがある。 活魚はイケス料理屋を除き、末端まで活かされることは少ない。魚は殺した直後はあまりうまくない。例えば、 以西底曳網やマグロ延縄では2・3日氷の上に放置した後で食膳に揚げられる。 活魚は、夕食にサシミとして消費されるときに、最も味と歯ざわりがよくなるように、時間を見て絞められる。
 [No.10: ft_image_50_14m/image079.jpg]
No.11
琵 琶 湖
 [No.1: ft_image_50_14m/image083.jpg]
No.2
No.3
No.1は競まで漁獲物を保管するイケスである。コンクリート製で、FRPが普及する前からあったことが伺える。 No.2はカゴで漁獲されたエビを運ぶトラックのタンクの中の写真である。活きた小エビは釣の餌として高価で 取引される。 No.3は淡水漁業による漁獲物である。佃煮等に加工されるので量の割には高価である。
|