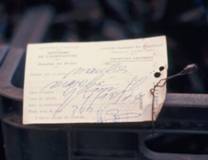|
漁業技術の画像集・FishTech
著作者/水産大学校名誉教授・理学博士 前田弘
Back to: Top Page |
FishTech 目次 | ご覧のページ
|
|
第 5 部 13 チュニジアの漁業 1976年11月から12月にかけて、チュニジアのMahdiaに国立漁業センターを設立するための事前調査団に参加した。 この機関は政府の職員と水産関係の再教育を目的と考えられていた。その基礎資料を集めるために、北はBizerte から南はJerba島までのチュニジアの海岸線のほぼ全体にわたって、主な漁村・水産関係の教育機関と政府機関を 訪問した。その際に撮影した写真を取りまとめたものある。 その後25年を経ているので、現在ではかなり変化した漁業もあれば、ほとんど変わっていない漁業があると 考えられる。また、消滅した漁業があるかもしれない。この写真集は、それらを知るためである。
159枚の写真は、次の5つのフォールダーに分け、MicrosoftのWordで入れてある。
 [No.1: ft_image_5_13/image001.jpg]
No.2
No.3
No.4
No.1 地中海型のトロール船 (La Goulette) この船は鉄船で、どちらかと言えば近代的とみなせるが、先の 特徴を備えている。方向探知機とレーダを備えている。しかし、これらは他の船にはほとんど付いていない。 No.2 地中海型のトロール船 (La Goulette) No.3 Kelibia港に入港中の地中海型トロール船 この船はKelibia水産高校(チュニジアの水産高校中では最も 水準が高いと言われる)の練習船であり、実習に重点を置くこの国では、学生は在学期間のほぼ半分をこの船で 過ごす。学校はこの港に面する(政府機関等No.11)。正面はフェニキア・カルタゴ・ローマ時代の砦で、ここから シシリア島が見える。 No.4 地中海型のトロール網 網は著しく長く、袖網の先端は大きな目合いであるが、身網に近づくに従って 目合いは次第に小さくなり、コッドエンドの目合いはかなり小さい。網の長さに比べて、ヘッドロープと グランドロープは短く、比較的細い。これは、限られた力で大きな網を曳く方法の1つである。日本でも、 地中海型トロールと似た考え方の網が和歌山県の箕島等で見られる。
 [No.5: ft_image_5_13/image009.jpg]
No.6
No.7
No.8
No.9
これまでに示した船はいずれも鉄船だが、チュニジアには大きな木造のトロール船も見られる。 No.5 入港中のトロール船 拡大すると、地中海型のトロール船の船型の特徴が見られる。 No.6 出港中の沿岸漁船 肩幅が広い。チュニジアでは、小型漁船でも主機関として船内据付け型の低速 ディゼルを備える。大きさの割に出力は小さいが、自力で修理できる特徴があり、これが堅実な国民性に適している。 三重刺網を使う。ネットホ−ラはない。この船は5人乗りである。反数は多くないが、このように多人数乗り 組むことがチュニジアの沿岸漁船の特徴である。 No.7−No.8 地中海型のトロール船の特徴を見るために付加えた。
No.9 基本的には地中海型トロール船の特徴を備えている。伝統的な地中海型トロール船ではSfaxに停泊して
いる船に見られるように、船尾は丸い。しかし、この船では角型で、無動力のローラがある点が進んでいる。
Lampara net(=Lamparo)と呼ばれる巻き網は、地中海起源で、日本の揚繰網と似ている。網船・1隻か2隻の 灯船・運搬船等が1組になり、灯火を利用して浮魚類を漁獲する。このような形態の漁業は、漁船が動力化する 前から漁業が盛んであった他の国でも見られる。 夕方に出漁し、1晩中集魚灯を点灯してイワシ類を集める。夜明け近くになると、少し離れたところに網船 が網を設置し、その上に集まった魚群を誘導して漁獲する。 その漁獲物はいわゆるアンチョビー(醗酵させた塩蔵の小型イワシ類)に加工されるか、日本の煮干に似た 型に加工され、国内で広く消費される。例えば、ほぼ1日に1回は食べるチュニジア風サラダには1尾か2尾の アンチョビーが付いている。煮干は地方の露店でもよく見られる。
 [No.1: ft_image_5_13/image019.jpg]
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
No.16
No.17
No.18
No.2 Mahdiaの魚市場 No.3 1組のLampara netの船団 中央の2隻は灯船 左は網船 No.4 1組のLampara netの船団 手前は灯船 やや大きい2隻は運搬船で、これらを曳航する。 No.5 右の大きな船はトロール船 小さな船が1組のLampara net船団で、右との手前は灯船(水上灯が 見られる)、中央2隻は網船、左は運搬船 No.6 灯船 低速ディゼルの主機が発電機の動力を兼ねる。水中灯を使う。 No.7 灯船 2基の水上灯と1基の水中灯を使う。 No.8 灯船 1基ずつの水上灯と水中灯を使う。この船型では速力はでないが、安定しており、作業をしやすい。 岸壁には、数統の網を揚げてある。Lampara netの網は長い袖網がある。これは端近くは大きな網目であり、 身網に近づくに従って目合いは小さくなる。身網はあまり大きくない。したがって、積み上げられた体積から 考えられるよりも長い。 No.9 網船 先の写真にも見られるように、灯船とほとんど大きさは変わらない。船は小さく、網は船に 比べても小さい。右舷船首近くに簡単なネットホーラーを備える。(刺網漁船でも、この程度のネットホーラー を付ければ役立つと考えられるが、ネットホーラ−が付いているのは、Lampara netの網船だけである。) No.10 網船 右舷中央付近にはネットホーラーが見られる。 遠景中央の桟橋には、網が見られる。中央の桟橋の反対側には数隻の灯船が繋いである。 No.12 網船 網は船に比べて小さい。旋網系統と考えると網目は小さく、網糸は 細い。網の浮子は刺網に比べると多いが、他の国の旋網よりは少ない。これは、Lampara netには環締め装置がなく、 巾着網と操作法が異なるためである。 No.13 陸上に広げられている網 色から考えるとLampara netである。 No.14 マグロ旋網 (La Goulette) ONP(政府機関等No.4とNo.5において説明する)輸入したが、漁労長が いないので、稼動していないとの説明であった。しかし、網の規模がマグロを狙うには小さ過ぎるし、魚函の 大きさ考えると、イワシ巾着網船の可能性がある。 No.15−No.16 No.14に示した船の部分拡大である。Purse winch、purse davit、環をかけるピンはpurse seinerの特徴を備える。 No.17 同船尾部 網は小さい。
No.18 浮子は他の国における巻き網と同程度の密度である。
 [No.1: ft_image_5_13/image055.jpg]
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
|
No.10 ベランダネット 中近東からアフリカにかけて、ボラを漁獲する独特な漁法が多い。これはその 代表的なものの1つである。漁獲されたボラは、塩と交互にタルに詰められ、広く取引される。
 [No.12: ft_image_5_13/image077.jpg]
 [No.13: ft_image_5_13/image079.jpg]
No.14
No.15
No.16
No.17
No.18
 [No.19: ft_image_5_13/image091.jpg]
No.20
No.21
No.22
No.21−No.22 7kgずつ袋に詰めて、航空貨物として輸出される。
 [No.23: ft_image_5_13/image099.jpg]
No.24
No.25
 [No.26: ft_image_5_13/image105.jpg]
No.27
No.27 タコはチュニジアではよく食べられる。足を結んでかなりの時間地面に叩き つけたあとで調理すると柔らかくなる。その他にも、タコを結んだ干物が露店の市場で売られている。流通の No.40では秤の台に載せられているのが、その製品である。同じような製品が地方の露店でも見られる。
 [No.28: ft_image_5_13/image109.jpg]
No.29
No.30
No.31
No.32
No.33
No.34
No.28 La Gouletteの漁港(Tunisの外港) 中央の桟橋に見られるほとんどの漁船は刺網を用いる。 No.29 ここで見られるほとんどの漁船は刺網を用いる。刺網は使用後、かかっている海藻等を陸上で外し、 破れた部分を補修し、棚で乾かす等の設備が近くにあるはずだが、そのような設備は見られない(これは他の 漁港でも見られないので、この国ではこのような習慣はないと考えられる。) ほとんどは三重刺網である。 No.30 三重刺網 浮子・沈子ともに少ない。 No.31 Monofilamentの刺網 使ったままで置いてあった。 No.32 三重刺網の補修(La Goulette) No.34 (La Goulette) これまで示した船にはネットホーラはなかった。この船にはその代わりに右舷船首 付近にプーリがある。この写真だけでは、Lampara netの網船の可能性が考えられるが、付近にはLampara netの 灯船等がなく、刺網船と考えられる。機関室の前に枠がある。これは他の刺網漁船にも見られるので、漁法と 何らかの関連が考えられるが、詳細は不明である。
 [No.35: ft_image_5_13/image123.jpg]
 [No.36: ft_image_5_13/image125.jpg]
No.37
No.38
No.39
No.37 Lateen sailで帆走する刺網漁船(Sfax) No.38 刺網漁船(Sfax) 5人が乗組む。 このように1隻の船に多くの人が乗組むことがチュニジアの特徴 である。中央から船尾にかけて枠が3つ見られる。 No.39 刺網 整理されていない。
 [No.40: ft_image_5_13/image133.jpg]
 [No.44: ft_image_5_13/image135.jpg]
No.45
No.46
No.47
No.48
No.50
No.51
No.52
No.42 ローンによって作られた漁船で5人が働く。 No.43 底延縄漁船 (Gabes) 鉢は深く、1鉢の幹縄は長い。この船でも3人が働く。岸壁には刺網がある。 No.44 刺網 No.45 刺網による漁獲 4人で働いて、1日の漁獲はこれだけである。束ねたものを単位として売る。 No.47 この漁船は帆走する。
 [No.53: ft_image_5_13/image151.jpg]
No.54
No.55
No.56
No.57
|
 [No.1: ft_image_5_13/image161.jpg]
No.2
No.3
No.4
 [No.5: ft_image_5_13/image169.jpg]
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
No.16
No.17
他にも果物・エビ・タコ等の缶詰を作るとの説明であったが、試作品かどうか分からなかった。大きな香料 倉庫があり、ここの製品は国内向けに独特の風味をつけているらしい。 No.2 缶詰プラント No.3 全景の模型 No.4 その右端に続く。 No.5 ここで使うMadragueの模型 No.6 Madragueの漁獲の水揚げ場 No.7 FAOが推薦したFerro-cementの船 No.8 大きなマグロは頭を下にして尾柄で吊下げてこのレールで運ばれる。 No.9−No.11 アンチョビーの加工プラント No.12−No.13 フィッシミールプラント 缶詰の残滓でフィッシミールを作る。 No.14 缶詰の外に付いたアブラをおが屑でとる。 No.15 アンチョビーの製造 カンに塩とイワシをこのように入れて、コンクリートの重しを乗せ、夏では 15日、冬では約45日置いて、巻締める。 No.16 ここの製品 No.17 SfaxのONPの製品
 [No.18: ft_image_5_13/image195.jpg]
No.19
No.20
No.21
No.22
No.23
No.24
No.25
No.26
No.27
No.28
No.29
No.30
No.31
No.32
No.33
No.34
No.35
No.36
No.37
No.38
No.39
No.40
No.41
No.42
|
集荷市場あるいは卸売市場の機能はONPが果たしている。これは一般消費者向けの小売市場である。 各店はある程度専門化している。価格はkg当たりのDinarで表示してある。当時、1 Dinarは約700円であった。 No.18 全景 正面にはONPの販売コーナー、右の外には野菜市場がある。 No.19 マグロの専門店 マグロは輪切りにして売る。頭は0.4 Dinar、切り身1.6 Dinar、カラスミ17 Dinar No.20 トロールの漁獲物は箱単位で仕入れる。 No.21 小型のカツオ類専門店 No.22 下に草を敷き、魚を立てかけて売る。シタビラメ2.16 Dinar No.23−No.24 ウナギの専門店 No.25 マグロの切り身の専門店 No.26 スズキに似た魚2.16 Dinar、クロダイ1.98 Dinar No.35 ムラサキイガイを売るときには衛生局の検査証が必要である。 No.38 ONPで作ったアンチョビーはカンをあけてバラ売りされる。 No.39 ONPで作った缶詰の専門店 缶詰は壁際に立てかけて売られる。このような展示法は中近東の他の国 でも見られる。 No.40 ここで扱われる缶詰 秤の台の上にはタコの干物である。 No.41 海綿は国内向けにも売られる。
 [No.39: ft_image_5_13/image245.jpg]
No.44
No.45
No.46
 [No.47: ft_image_5_13/image253.jpg]
No.48
No.49
No.50
No.51
No.52
No.53
No.44 地方にあるONPの魚屋 No.45−No.47 ONPがSfaxに作った網工場(建設中) STUFINと呼ばれる。主にトロール・Lampara net及び 定置網用の網地を作るためとの説明であったが、ラッセル網の編網機しかなかった。 No.48−No.50 ONPの集荷市場(Gabes)とその内部
No.51−No.53 ONPが作った販売市場(Gabes)とその内部
 [No.1: ft_image_5_13/image267.jpg]
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.2−No.3 水産局 No.4−No.5 ONPの本部 チュニスとカルタゴの間にある。Office National des Peches 1958年に設立、 1969年までは水産物の流通販売の独占権をもっていた 国による企業 No.6 INSTOP(Institut National Scientifique et Technique d’Oceano-graphie et de Peche) チュニスの 北郊のカルタゴ時代の商港と軍港にはさまれた所にあり、1924年に設立され、基礎的な漁業研究を行う。調査船 の乗組員を含め約120名の組織で、そのうち約10名が研究者である。 No.7 INAT (チュニス国立農業大学)(Institut National Agronomique de Tunisie)2年課程の水産コース があり、政府の上級職員を養成する。
 [No.8: ft_image_5_13/image281.jpg]
No.9
No.10
チュニジアにおける水産に関する教育機関には次の3段階がある入学資格と修業年限はコースと学校の水準
によって異なる: CFPP 漁業職業訓練所 (Centres de Formation Professionelle de Peches) 一般漁夫・機関員・船大工を養成する。 CTCP 漁業訓練所 (Centreds de Travail Civil des Peches) 主として一般漁夫を養成する。
 [No.11: ft_image_5_13/image287.jpg]
No.12
No.13
No.14
No.15
No.16
No.17
No.11 前景は校舎 道路の先は実習室で港に続く No.12 正面 No.13 授業 No.14 木造船建造実習室 No.15 その内部 実技に重点を置く傾向が分かる。 No.16 機関のモデル 日本の学校におけるよりも、標本や模型等に重点が置かれている。 No.17 網作業実習
 [No.18: ft_image_5_13/image301.jpg]
No.19
No.20
No.21
 [No.18: ft_image_5_13/image309.jpg]
No.19 同減圧タンク 職業訓練的色彩の強いことが伺える。 No.20 CFPPの宿舎 No.21−No.22 CTCP
|