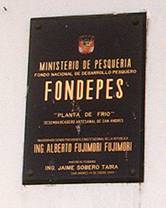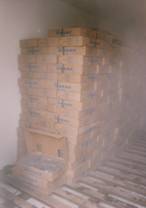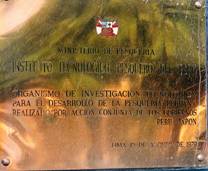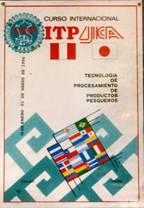|
漁業技術の画像集・FishTech
著作者/水産大学校名誉教授・理学博士 前田弘
Back to: Top Page |
FishTech 目次 | ご覧のページ
|
|
第 6 部 23 ペルーの漁業 ペルーは、一時世界一の漁獲量を誇っていた。しかし、これはアンチョビー1魚種に頼り、その後海況の変動に加えて、 フィッシミールの市況の低迷から、さらに国内政情不安の影響を受けて、漁獲量は大幅に減少した。 海況の変動の中で最も有名でしかも世界に影響を及ぼすのは、エル・ニーニョ現象である。しかし、この調査に 当たる船は老朽化していた。その代船を供与する計画は以前から立てられていたが、ペルーに対する調査団や専門家 の派遣は、政情不安のために一時中止された。 1996年には短期の調査団の派遣は再開されたので、3月に3週間の日程で事前調査団の1員としてペルーに派遣された。 以下は、その際に撮影した写真を収録したものである。 ゲリラによる大使公邸占拠という前代未聞の事件が起きたのは、帰国後調査レポートを製作し、それを受けて基本 設計調査団が派遣されるまでの間のことである。 派遣中断前には、カメラを持って魚市場に入ることは考えられず、ひったくりに遭わずに帰られる可能性は極めて 低かった。そのために、写真は車内から撮るか、使い捨てに近いカメラによらなければならなかった。 事故再発による再度の協力中断を避けるために、行動は極端に制約を受け、(1)Callaoの漁港、(2)Limaの町外れに 近い漁村、(3)Piscoの漁村、(4)その近くのSan Andresの漁村しか見学できなかった。したがって、ここに示す 写真は、国全体の水産事情を説明するには十分でなく、(1)はかって世界一の水揚げを誇った巾着網船団の片鱗を 伺えるに過ぎない。他方ペルーでは、酢でしめたサシミに近いセビチェで代表されるように、海産物を好む習慣が 深い。その魚を供給する漁村に対し、政府が力を入れている様子を示すために(2)から(4)を示した。その他に、シー フードレストランとスーパーマーケットにおける魚コーナー及び研究機関の写真を(5)として付け加えた。なお、テロ 防止のために政府の機関に関する写真は極めて限られる。
1 Callaoの漁港 1 Callaoの漁港 2台のカメラで撮ったので、よく似た写真が2枚ずつある。しかし、わずかずつ違うので、細かな情報まで引出す ために、すべてを上げる。
No.1-1
No.1-2
No.1-3
No.1-4
No.1-5
No.1-6
No.1-7
No.1-8
No.1-9
No.1-10
No.1-11
No.1-12
No.1-13
No.1-14
No.1-15
No.1-16 No.1-1、No.1-2及びNo.1-4は標準レンズ、No.1-3及びNo.1-5は110mm、No.1-6―No.1-13、No.1-15及びNo.1-16は 200mmレンズで撮影した写真の必要部分を、パソコンでトリミングし、拡大して収録したものである。したがって、 装備等の詳細をみるのには適さない。概況と船団の規模を知り、単一の表層魚を対象とした漁業における対象魚種 の資源量の変動が及ぼした影響を感じ取って欲しい。 大部分はpurse seinerで、ターンテーブル方式から、power blockで網を上げる方式に変わった時代、すなわち、 1970年代から80年代に建造された船である。この時代はペルーが世界最高の漁獲を揚げ、国内の治安が悪化する 以前に相当する。 探魚のためのヘリコプターは搭載していない。Skiffを搭載していることは分かる。 これだけの船団が繋船状態にあるのは、休漁期あるいは漁獲量制限のためでない。その漁獲物を処理するプラント からさらにそれらを補修する産業等が休止状態になることを意味する。 漁港には、No.1-14―No.1-15に見られるように、海鳥が多い。その他の写真にも海鳥が写っている。これはPisco の写真でも見られる。このように鳥が多いのは、ペルーの特徴で、この糞が有名なGuanoのもとである。これからも、 近海における浮魚類の多いことが分かる。 No.1-1、No.1-2及びNo.1-4 これらは、ほぼ同じ被写体を標準レンズを用いて撮った写真である。これらから、 各船の構造等の詳細は読み取れないが、繋留されているのはほとんどがpurse seinerであり、その多さが分かる。 No.1-3、No.1-5 110mmレンズを用いて撮った写真である。写っている船は、ほとんどがpurse seinerである。 日本では、同じ漁業に従事する船でも、1隻ずつ構造が異なる。ここでは、詳細に見ると数通りの船型しかない ことが分かる。これは船に対する考え方あるいは雇用に関する形態が異なるためである。 No.1-6 少し方向を変えた撮った写真である。左の端はpurse seinerである。 No.1-7−No.1-12 200mmレンズを用いて撮った写真である。拡大すれば、辛うじて船型が分かる。Power blockを 使って網を揚げる方式である。船尾は斜面になり、skiffを引揚げてある。 No.1-13 これらもpurse seinerである。これまでの写真に写っていたものと比べるとはるかに小さい。フイッシュ ミール原料のように、漁獲量だけが問題になる場合、これらのように大きさが著しく異なる船が競合できるか疑問 である。 No.1-14 この多い鳥の餌になるアンチョビーが、これまでに見せたpurse seiner船団とフィッシュミール産業 を支える。 No.1-15−No.1-16 これまでに示した写真はいずれもフィッシミールを作るたるためのアンチョビーを漁獲する purse seinerであった。しかし、これらは船尾式のトロール船である。ペルーでは大陸棚が狭いので、これらが 着底トロールを使って輸出原料の底魚類を漁獲することも、中層トロールを使ってpurse seinerと同じフィッシュ ミール原料のアンチョビーを漁獲することも考えにくい。最も可能性が高いのは、一時この海域で日本のトロール 船が行ったように中層トロールのよってアジを狙うことである。
No.1-17 No.1-17 Callao港に唯一着岸していた漁船は、補給のために入港していた日本のマグロ延縄船であった。
No.1-18
No.1-19 No.1-18−No.1-19 ペルー海洋学研究所の前に停泊していた底延縄漁船 この付近ではこの程度の大きさの 漁船は、この他に数隻のpurse seinerだけであった。 2 Limaの町外れに近い漁村 これまでに記したpurse seinerはペルーにおける漁獲の大部分を揚げるが、どちらかといえば一般市民の食料 とは直接関係のないフィッシミールの原料を漁獲するだけであった。 一般市民の魚を食べる習慣を支える漁業の一例として、Limaの町外れに近い漁村において、漁業財団(FONDEPES) が沿岸漁業振興のために作った水揚げ施設の写真を示す。これは海水浴場から突出した桟橋である。そこでは一般 市民向けに漁獲物を販売するとともに、簡単な魚レストランがある。これがペルーにおけるこのような設備の特徴 である。
No.2-1
No.2-2
No.2-3
No.2-4
No.2-5
No.2-6
No.2-7
No.2-8
No.2-9
No.2-10
No.2-11
No.2-12
No.2-13
No.2-14
No.2-15
No.2-16
No.2-17 No.2-1−No.2-2 ほとんどの漁船は一本釣と刺網を用いる。(背景はLima、 厳密には、Limaはいくつかの都市 が集まって作る首都圏metropolitanaの1つの都市である。しかし、ここでは首都圏を仮にLimaと呼ぶ) No.2-3 財団が作った上屋 No.2-4−No.2-5 その近くで漁具を修理する。漁具はmonofilamentの刺網で、丈は高い。No.2-5の背景は桟橋 である。遠浅の海岸なので、ここに水揚げする。この桟橋には水揚げのためのデリックや冷蔵庫のような荷役に直接 関係のある固定設備はなく、No.2-7からNo.2-17に示すような設備がある。 No.2-6 刺網を載せた漁船 据え付け機関や帆走設備はない。Transom sternになっており、推進には船外機を 使うと考えられる。ネットーホーラや揚網の補助となるプーリはない。 No.2-7 桟橋の先端にある魚売り場 ここでは魚をさばいて売るが、そのための設備―例えば水道―はない。 No.2-8−No.2-14 桟橋の先端にある魚屋は、ある程度店毎に扱う魚種は異なる。 No.2-15 この店は魚料理を食べさせるかどうか分からないが、魚の他にも菓子やコーラ等を売る。すなわち、 この施設は簡単なリクリエーションセンターの色彩を備える。 No.2-16 この店では魚を食べさせる。右の皿はセビッチェで、セビッチェを食べる習慣の広さが分かる。なお、 写真では示せなかったが、市内には市民が普通に入れるようなセビチェ店が見られる。 No.2-17 前景の店では、魚を食べさせるかどうか分からないが、遠景の店では魚料理(セビッチェやフライの ような簡単なもの)を食べさせる。 3. Piscoの漁村 PiscoはLimaから約150km南にある。Piscoまで4名の武装した護衛付きで視察にでかけた。これはその際に撮影 した写真である。(滞在期間が短かったことと、当時の治安状況から考えて、陸路ではこの程度までしか行け なかった。)
No.3-1
No.3-2
No.3-3
No.3-4
No.3-5
No.3-6
No.3-7
No.3-8
No.3-9
No.3-10
No.3-11
No.3-12
No.3-13
No.3-14
|
 [No.3-15: ft_image_6_23/image101.jpg]
No.3-16
No.3-17
No.3-18
No.3-19
No.3-20
No.3-21
No.3-22 No.3-1 海から見た魚の処理プラント No.3-2 Piscoの船溜りは海水浴場にある。ここは南緯14°とはいえ、寒流が流れている。したがって、日差しは 強くても水温は低く、海水浴客はほとんど海で泳がない。この寒流のためにすぐ近くに豊富な漁場が形成される。 No.3-3−No.3-9 種々の型の漁船が泊まっていたが、ほとんどは小型である。中にはそれらよりやや大きな―日本 でいえば小型の― purse seunerが見られ、沖合いにはCallaoで見られたような大型のpurse seinerが見られた。 この大型のpurse seinerの荷役はバージによる。 No.3-5 左端に見られるのは観光船用の桟橋で、黄色の船は観光船である。 No.3-10−No.3-12 ここは地上絵で有名なNazcaから200km離れているが、それでも地上絵が見られる。 No.3-13−No.3-14 海鳥の糞でできたguanoは化学肥料がなかった時代から肥料として有名であった。近くの島は guanoで被われている。Guanoは政府が厳重に管理し、数年おきに採掘する。その施設とguanoが島を被っている様子 を示す。 No.3-15 餌となる魚が豊富なので、島には多数の海獣類が休息している。 No.3-16 遊泳している海獣類 左端は潜水してイボニシ(Thais choolta)を取る漁船 No.3-17−No.3-20 潜水漁業をしている漁船 この漁業は3・4名で行う。漁場までの往復には船外機を用いるが、 操業中はオールで船を操る。潜水器の型は分からないが、送気ポンプの動力は低速ディゼルである。 No.3-21−No.3-22 日本が供与したマリンビーフプラント 原料の1次処理のスリミプラントは、工船のものと ほとんど変わらない。休止していた。 4.San Andresの漁村 San AndresはPiscoの北に隣接する漁村である。漁業財団が作った漁獲物の荷役用の桟橋と、それに付帯した簡単 な冷蔵庫がある。
No.4-1
No.4-2
No.4-3
No.4-4
No.4-5
No.4-6
No.4-7
No.4-8
No.4-9
No.4-10
No.4-11
No.4-12 No.4-1−No.4-3 ここはPiscoのすぐ近くであるが、Piscoで見られたような大型と中型のpurse seinerは 見られず、すべてが小型の沿岸漁船であった。そのほとんどは船外機を備え、No.4-3ではYamahaの代理店が 見られる。 No.4-4−No.4-5 漁業財団が作った施設 その入り口には露店があり、そこでは菓子やコーラ類の他に、 簡単なセビッチェと魚のフライを食べさせる。 No.4-6−No.4-7 1981年6月28日にこの施設が完成した。このような施設には、ここに示したような銘板がある。 No.4-8 事務所 No.4-9 ペルーの漁村では貝類をよく見かける。 No.4-10−No.4-12 冷蔵庫とそれに付帯する簡単な処理施設 5. 流通・研究機関等
No.5-1
No.5-2
No.5-3
No.5-4
No.5-5
No.5-6
No.5-7
No.5-8
No.5-9
No.5-10 No.5-1−No.5-5 スーパーマーケットの魚コーナー No.5-5では前処理をした貝類を売っている。 No.5-6−No.5-7 スーパーマーケットの海産缶詰コーナー No.5-8−No.5-10 Limaの海水浴場の近くには高級なシーフードレストランがあり、賑わっていた。しかし、 ここは一般市民向けでない。No.5-8はそのスシコーナーである。生のままで海産物を食べる習慣がある。
No.5-11
No.5-12
No.5-13
No.5-14 No.5-11−No.5-14 ペルー海洋学研究所(Instituto del Mar del Peru) Callaoにある。 No.5-11 陸より No.5-12 海より No.5-13 入り口のガードマン ペルーでは、政府の機関ばかりでなく、民間の会社や事務所等でもガードマン で守られている。我々が泊っていたホテルも、夜間には柵を閉めてガードマンが警戒していた。(官庁は撮影 禁止であった。) No.5-14 研究所の桟橋 オッターボーや漁網のような重くて扱いにくい調査・研究資材でも、この桟橋から 調査船までは交通艇で運んでいた。
No.5-15 No.5-15 北部やその他の地方では干草を束ねた船で漁業をしている。これは造船所に飾られていたものである。
No.5-16
No.5-17
No.5-18
No.5-19
No.5-20
No.5-21
No.5-22
No.5-23 No.5-16−N0.5-17 水産加工研究所(Instituto Tecnologico Pesquero del Peru、ITPと呼ばれる)は魚市場の 近くにある。魚市場の入り口に近い露店の中にはセビッチェや魚のフライを食べさせる。 No.5-18−No.5-20 日本の援助で作られた水産加工研究所 外側はレンガ塀で囲まれ、その上には高圧電線が 張られ、見張台がある。入り口は鉄の扉である。 No.5-20 そのマークはインカ風である。 No.5-21 1979年8月19日にJICAの援助で作られたことを示す銘板 No.5-22 ITPの建物 No.5-23 ゲリラ等に対して厳重な警戒をしているが、それでもJICAの援助で3国研修が行われていた。その ポスター
No.5-24
No.5-25
No.5-26
No.5-27 No.5-24−No.5-27 内部 日本の研究所と異なり、実用向けの試作品を作るような傾向が強い。
No.5-28
No.5-29 No.5-28−No.5-29 南太平洋漁業委員会 コロンビア・エクアドル・ペルー・チリーの4カ国の連絡機関で、 事務局は1年ごとの回り持ち ペルーの沿岸零細漁業に関して、La Pesqueria artesanal en el Peru durante junio de 1986 a junio de 1988を翻訳し、「ペルーの沿岸小規模漁業」として海外漁業協力財団より発行した。それによれば、各地の漁村 では漁業の原点といえるような漁業がある。例えば、バルサ材を集めて作った船あるいは干草を束ねた船を使った 漁業等である。これらを見られることを期待していた。しかし、調査期間が短く、先に記したような国情のために、 その機会に恵まれなかった。漁業の原点を見る意味で先に記した翻訳を参照して欲しい。
|