海洋辞典 |
海洋辞典 |
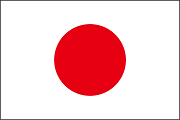
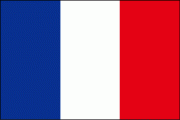
和仏/分野別 海洋辞典
漁具漁法用語
仏和/和仏
|
abari網針(あばり): → navette: n.f.[海・漁]網すき針、網針(あばり)[漁網を編むのに用いる]; ひょうたん形滑車、シスターブロック; シャトルのように 往復すること; [近接する2点間で往復する船・バスなどの]連絡便、シャトル便、[船・列車・バス・飛行機などの近距離間の] 折り返し往復便; [織]杼(ひ)、シャトル; [ミシンの]中釜(なかがま); 船形の香入(こういれ).
ago[釣り針などの]あご: → aguあぐ: → あご.
ami網: →
/barander: v.i.網で川を塞いで魚を捕る(獲る). /barrique: n.f.大樽; 一樽の容量; [漁]ヤツメウナギ網. /bichette: n.f.小えび網. /bourdon: n.m.[漁][立て網の]棒、網を立てる棒. /bretelle: n.f.[漁]つのざめ網. /bretellière: n.f.ツノザメ網. /cache: n.f.[魚を捕る]網; [獲物の脱出を防ぐための囲いの出口に張る] 網. /caudrette: n.f.[漁]イセエビ網、エビ網、[エビなどを捕る] 袋網、ザリガニ用網. /cibaudière: f.ボラ網、[目の粗い]漁網. /combrière: n.f.[漁]マグロ網. /crevettier: n.m.小エビ取り、小エビを採捕する舟、小エビ漁船; 小エビを採捕する網. /crevettière: n.f.叉手網(さであみ)、小エビ漁網. /dideau, eaux: n.m.[漁]橋弧の下に仕掛けた網. /emmailler: v.t.[魚を]網でとる. ・ s'emmailler: v.pr.(代名動詞)[魚が]網にかかる. /filet: n.m.[魚・鳥・昆虫などの動物を捕獲するための各種の]網、漁網(=filet de pêche); [物を支えたり包んだりする]網、 ネット; 網袋; [テニス・バレーボールなどの]ネット.
/[beau] coup de filet: 一網、一網の漁獲、[大漁]; 一斉取り締まり、[大量検挙]. /faire du filet: 網漁をする. /filet à poissons: 魚網. /filet de pêche: 漁網. /jeter un filet: 網を打つ. /mailler un filet: 網を編む. /monter un filet: 漁網を定置する. /pêche au filet: 網漁. /prendre du poisson au filet: 網で魚を捕る(獲る). /tendre un filet: 網を張る. /gabare, gabarre: n.f.[海]川で大きな船の荷の積み降ろしをする船、大型川舟; [河川・港湾用の]運送船、艀(はしけ)、 伝馬船; [昔の海軍の]輸送船、貨物輸送船; [漁]地引き網; [大西洋沿岸の河口で用いられる]漁獲網; 大型曳き網(→ n.m.小型曳き網: gabaret); 漁船の一種. /guideau(n.m., pl. ~x), guide-eau(n.m.inv.): [土木][港の入口などの]導流堤(どうりゅうてい)、 導流工; 排水を港外に導くために水中に斜めに設けた板、速い水流を導くために斜めに設けた敷き板; [海][港内の板でできた]排水路、堰(せき); [漁][川口に張る]捕魚網、長袋網、袋網. /laceur(se): n.[狩猟・漁猟(ぎょりょう)用の]網の作り手、網を編む人、網作り. /maillé, e: (maillerのp.p.)adj.[魚などが]網にかかった; [網・編み物などが]目のある. /mailler: v.t.[網などを]編む; [海][鎖などを、別の鎖に]連環で繋(つな)ぐ、[鎖の環を]つなぐ、シャックルで繫ぐ; [帆を]他の帆に紐でかがり合わせる. v. i.[網が]魚を捕える; [魚が]網にかかる. ・ se mailler: (v.pr.)[網が]魚を捕える; [魚が]網にかかる. ・ un filet qui maille bien: よく魚がかかる網. /mangue: n.f.[漁]漁網の一種. /maniolle: n.f.雑魚網. /matramaux, matrameaux: n.m.pl.漁網の一種. /muletières: n.f.pl.[漁]ボラ網. /pantière→ grande pantière: [漁][北フランスでの]漁網 [参考]pantière: n.f.[猟]かすみ網; [獲物を入れる]網袋. /pêche au filet: 網漁. /pêcher au filet: [目的語なしに]網漁をする. /picot: n.m.[漁][ノルマンディー沿岸での]漁網、[ノルマンディー地方でカレイ類をとる]網、底引き網; [偏平の 魚を獲るための]漁網. /pochette: f.[漁・狩]小網; 小さいポケット. /rafle: n.f.一斉検挙、手入れ; [軍][大砲などの]速射; [漁][複数の入り口のある]漁. /ramender: v.t.[網・漁網を]繕(つくろ)う、修理する→ ramendeur(se): n.[船上で]魚網を繕(つくろ)う人、[漁船の]網を修理する人. /rèdre: n.m.ニシン漁用の大網. /rets: n.m.[古語][漁労・狩猟用の]網; わな. ・ tendre des rets: 網を張る. /rieux: n.m.[河川用の]漁網. /roulée: n.f.[ロワール川で用いられるヤツメウナギ用の]漁網. /salabre: n.m.[漁]手網、曳き網. /sédor: n.m.一種の鮭漁網. /ségétière: n.f.大漁網の一種. /six-doigts: n.m.[漁]荒目網. /socletière: n.f.[漁]小イワシ網 [参考]soclet: n.m.[魚][地中海の]小イワシ. /thonaire: n.m.[漁][地中海で用いられる]マグロ網、鮪網(しびあみ). ・ thonier, ère: adj.マグロ[漁]の、n.m.マグロ漁船; マグロ漁師. /truau, aux: n.m.漁網の一種. ami-gakoi網囲い: → 生け簀.
amime網目: → maillage: n.m.[漁]網目の大きさ.
・ filet à mailles larges, filet à larges mailles: 目の大きな網、目の広い網. ・ glisser entre les mailles d'un filet: 網の目をくぐる. /maillon: n.m.小さな網目. /pigeon: n.m.鳩(はと)[類][ハト科の鳥の総称; 特に雄鳩]; [漁][投網(とあみ)の]へり網の目、[網の]編み 始めの目、[漁網の編み始めの部分の]半目. arame-ami[漁]荒目網: six-doigts(m). ana[魚の潜む]穴: → crône: n.f.[漁]魚の潜む穴、[川岸近くの]魚が潜む淵、[木の根などを沈めた]魚の寄り場; 起重機.
atari当たり: → touche: n.f.触れること、接触; [絵画の]タッチ、筆触; [釣りでの魚の]当たり、食い、ヒット、[魚が餌を]ちょっとかむこと;
[サッカー・ラグビーなどの]タッチ.
awase[釣]合わせ: → ferrage: n.m.鉄具をつけること; 金具類; [釣][餌を食いに来た魚の]合わせ.
bou棒: → bourdon: n.m.[漁][立て網の]棒、網を立てる棒.
doramuドラム: → tambour de demorque: 引き船のロープのドラム. do-ri-ドーリー: → doris: [米語]n.m.[漁]ドーリー[ニューファウンドランドで延縄(はえなわ)を敷くための平底舟]; [鱈(たら)を 釣るための]平底漁船、平底鱈漁船、[鱈漁用の]平型漁船.
en'you-gyogyou遠洋漁業: grande pêche.
esa餌(えさ): →
/amorce: n.f.[魚の]餌、[魚釣りなどの]餌(えさ)、まき餌; [獲物をわなにおびき寄せる]えさ. ・ amorce vive: 生き餌(え). ・ mettre l'amorce à l'hamec,on: 釣り針に餌をつける. ・ mordre à l'amorce: 餌に食いつく. ・ se laisser prendre à l'amorce: [魚が]餌にかかる. /amorcer: v.t.[釣り針・釣り糸に]餌(えさ)をつける; [水に]餌をまく、[餌で]おびき寄せる; [魚・獲物を]餌で おびき寄せる. ・ amorcer l'hameçon: 釣り針に餌をつける. ・ amorcer des poissons: 撒き餌(まきえ)で魚を引き寄せる・おびき寄せる. ・ amorceur, euse: n.餌をつける人、餌を撒く人. /amorçoir: n.m.[漁][水底に餌をまく]まき餌(え)道具、まき餌(え)箱; ボートぎり. /appât: n.m.[魚・鳥の捕獲用の]餌(えさ); 誘い、誘惑. ・ appâts de fond: 撒き餌. ・ appât vivant: 生餌(いきえ). ・ attirer des poissons avec de l'appât: 餌で魚をおびき寄せる. ・ mettre l'appât à l'hameçon: 釣針に餌をつける. ・ mordre à l'appât: [魚が]餌に食いつく. /appâter: v.t.[魚・鳥などを餌(えさ)で]おびき寄せる、釣る; [釣り針・罠(わな)などに]餌をつける; [鳥に]餌を 与える. ・ appâter l'hameçon: 釣針に餌をつける. /attraire: v.t.[古][餌で]おびき寄せる. /attrait: n.m.[釣りの]餌. /boëte, boëtte: n.f.[漁]釣り餌(え)、まき餌. /boitte: n.f.[漁][鱈漁用の]餌(えさ). /boitter: v.i.えさを捲(ま)く、撒き餌をする、v.t.[針に]餌をつける. /embecquer: v.t.[釣り針に]餌(えさ)を付ける. /enferrer: v.t.[人を]突き刺す; [漁][釣り針に]生き餌(え)をつける、[ミミズなどを]釣り糸につける. ・ s'enferrer: v.pr.[魚が自分から]針にかかる、餌に引っ掛かる、[魚が]釣り針を呑み込む. /esche: n.f.[釣][釣り針用の]餌(えさ)(=aiche). /escher: v.t.[釣][釣り針・釣り糸に]餌(えさ)をつける. /leurre: n.m.[漁][魚の]作り餌; 香餌(こうじ)、わな; [釣りの]ルアー、擬餌鉤(ぎじばり); [狩]おとり. /leurrer: (v.t.)[魚などを]おとり(作り餌)でおびき寄せる. /manne: n.f.→ manne des pêcheurs: 釣りの餌[[昆虫]カゲロウ、カトンボ]. /mordeur, se: adj.[魚などが]かむ習性のある、n.m.[餌(えさ)に]食いつく魚; [魚]スズキ(cf. bar). /pelote: n.f.[糸・毛糸などの]玉; [釣り針につけた餌(えさ)をくるむ]粘土塊. ・ peloter: v.t.[釣り餌(え)をくるんだ粘土塊を用いて魚を] 釣る.
fukuro-ami袋網(n.m., pl. ~x), guide-eau(n.m.inv.): →
/manche: n.f.袖(そで); 管、導管、ホース、筒; 海峡; 一種の漁業用袋網. /poche: n.f.ポケット; [魚網の端の]袋網、[トロール網などの]袋網; 網嚢; 漁業用大網. /venet: n.m.[漁][干潮時に魚が網に入るように、魚を導き入れる口を陸側に向けて張られた]張網、半円形建網、半円形定置網、 [干潮時を利用する]袋網.
funabiki-ami船曳網、船引き網: →
/dandinette: n.f.[漁][踊らせて使う]擬餌鉤(ぎじばり); ルアー釣り、擬餌針(ぎじばり)釣り. ・ pêcher à la dandinette: 餌を踊らせて釣る、擬餌針で釣る. /devon: [英語]n.m.[釣][釣りに用いる、魚の形をした]擬餌(ぎじ)針、擬似鉤(ぎじばり)、擬製魚、人工魚、ルアー. /leurre: n.m.[漁][魚の]作り餌; 香餌(こうじ)、わな; [釣りの]ルアー、擬餌鉤(ぎじばり); [狩]おとり. /leurrer: (v.t.)[魚などを]おとり(作り餌)でおびき寄せる. /poisson nageur: [漁]擬餌(ぎじ)、擬餌針、ルアー. /tue-diable: n.m.inv.[釣][鱒釣り用の]プラグ [擬餌針(ぎじばり)]、魚の形をした金属に釣針を付けた釣り具、擬魚. gyafuギャフ: → 魚鉤. gyogu漁具: engins de pêche. > gyohou漁法: → halieutique: adj.魚釣りの、釣りの、漁の、漁業の、n.f.漁法、n.m.pl.漁魚論. gyomou漁網: → 網.
gyosen漁船: bateau de pêche, bateau pêcheur/kajac: n.m.[グリーンランドの]アザラシ皮製の漁船
/palangrin: n.m.アルジェリアの沿岸漁船/picoteau: n.m.[英仏海峡の]帆掛けの小形漁船、二本檣の小漁船/
pinasse: n.f.[フランス西南部沿岸での]平底の漁船 [主にイワシ漁用]; [昔の]競漕(きょうそう)船; [古語]平底
の小型帆船/smack: n.m.[英語][オランダの]漁船/topo: n.m.[アドリア海の2本マストの]漁船/
trinquart: n.m.[漁]鰊(ニシン)船、小型鰊漁船.
/cordeau: (pl.~x)n.m.細縄、小綱; 綱、[海]引き綱; [漁]底延縄(そこはえなわ)、[浮きがなく、複数の針がついた]底釣りの糸. /cordée: n.f.[漁][底延縄(cordeau)に付けらえた]みち糸; [漁]延縄; [ウナギの]釣り糸; [綱で縛ったものの]一締め. /doris: [米語]n.m.[漁]ドーリー[ニューファウンドランドで延縄(はえなわ)を敷くための平底舟]; [鱈(たら)を 釣るための]平底漁船、平底鱈漁船、[鱈漁用の]平型漁船. /palancre, palangre: n.f.[漁]延縄(はえなわ)、浮き延縄、[釣り糸の一種]トロール釣り糸.
hariami張網: → gord: n.m.[漁][杭にかける]張網、簗(やな); 川に2列の杭を並べてその端に袋網をかけた漁場; 捕魚堰.
/pantène, pantenne: n.f.[魚・鳥を捕えるための]垂直の張綱(→ pantière); [猟]かすみ網、猟用網、わな. /vannet: n.m.[漁][干潮時に浜・海岸に張る(仕掛ける)]張網; 刺し網 [干潮時に浜に仕掛けて、満潮に乗ってやってくる魚を獲る; 主にニシン漁]. /venet: n.m.[漁][干潮時に魚が網に入るように、魚を導き入れる口を陸側に向けて張られた]張網、半円形建網、半円形定置網、 [干潮時を利用する]袋網. haridashi-zao張出し竿: → tangon: n.m.[海]ブーム [大三角帆の裾(すそ)を張る帆桁]; [軍艦の]張り出し桁 [小船を繋ぎ、水雷よけの網を張る]、 [海][ボートを係留する]張り出し桁(けた)、ブーム、[海]係船桁 [小舟を係留するための横木で、船外に張り出される]; [舷へ登る ための梯をかける]張り出し桁; [カツオ・マグロ漁船の]張出し竿. harihazushi針はずし: [参照]はずす.
harisuはりす: → avancée: n.f.[釣]針素(はりす)[おもりから針までの糸].
/empilage: n.m.[漁][釣り針を]針す(はりす・ハリス)につけること、はり素(す)につけること、鉤素(はりす)につけること; 積み重ねること; 堆積. /empile: n.f.[漁][釣り糸の先の]針す(ハリス)、はり素(す)、[釣り針をつける]鉤素(はりす)、[はり元(もと)の]先糸. /empiler: v.t.[漁][釣り針を]針すにつける. /pile: n.f.[漁][道糸(みちいと)から分れた釣糸についている]細い釣糸、針す、ハリス.
hazusu[鉤・釣り針などから]はずす:
・ décrocher le poisson: [掛かった]魚を釣り針からはずす. ・ décrocher un poisson: 魚を釣り針からはずす. /dégorgeoir: n.m.排水口; [池などの]流出口; [漁][魚の]針はずし、針外し、針はずし器、呑込鉤(はり)はずし; [昔の大砲の]洗桿(せんかん)、洗矢(あらいや). /désamorçage: n.m.[釣り針の]餌をはずすこと. /désempilage: n.m.釣り針を外すこと. /désempiler: v.t.釣り針を外す.
hikiami曳網、引き網(ひきあみ): →
/chalut: n.m.[漁]曳網、トロール、トロール網、底引き網. ・ pêcher au chalut: トロール網漁をする. ・ pêcher la morue au chalut: タラ(鱈)をトロールで獲(と)る. /chalutage: n.m.[漁]曳網漁業、トロール漁業、底引き網漁業. /chaluter: v.i.曳網(トロール)漁業をする、曳網を曳く. /chalutier(ère): adj.曳網(トロール網)で行う、トロールの、曳網の、底引き網の、n.m.(chalutier)トロール漁夫、トロール漁従事者、 底引き網漁夫、曳網漁夫; トロール船、トロール漁船、曳網漁船. ・ chalutier à vapeur: トロール汽船. ・ pêche chalutière: .[漁]曳網漁業、トロール漁業、底引き網漁業(=chalutage). /drague: [英語: drag(水底をさらう)]n.f.浚渫機(しゅんせつき)、ドレッジャー、土浚い道具; 浚渫船; [水底の物をひっかけて取る]かぎ、鉤; [漁][カキ・貝を採るための]すくい網、引き網; [漁][貝類を採る] 桁網(けたあみ)、[貝をすくう]掻き網; [海]浮錨; [海][水中の物体(特に機雷)を探すために船が曳(ひ)く]撈錨(ろうびょう)、[機雷除去 用の]掃海機. ・ pêcheur à la drague: すくい網の漁師. /drège, dreige: n.f.[漁]底引き網、曳網; 地引き網、地曳網. /drégeur: n.m.曳網漁船. /gabare, gabarre: n.f.[海]川で大きな船の荷の積み降ろしをする船、大型川舟; [河川・港湾用の]運送船、艀(はしけ)、 伝馬船; [昔の海軍の]輸送船、貨物輸送船; [漁]地引き網; [大西洋沿岸の河口で用いられる]漁獲網; 大型曳き網(→ n.m.小型曳き網: gabaret); 漁船の一種. /gabaret: n.m.小型の曳き網. /parmi: n.m.[海][引き網の縁索(ふちなわ)の間に張り渡した] 補強用ロープ. /pêche au trait: [船につけた]引き網による漁業 [参考]trait: n.m.線. /salabre: n.m.[漁]手網、曳き網. /seine: n.f.[漁]引き網(→ senne)、地曳網、地引網、地引き網. /seiner: v.t.[魚を]引網で取る、地引網で漁獲する、v.i.引網で漁をする、地引網で魚を取る、引網をかける. /seinette: n.f.[漁]小引網. /seineur, euse: adj.地引をする、n.m.地引漁夫. /senne: n.f.[漁]引き網(=seine). /senner: v.i.=seiner. /sennette: n.f.=seinette. /senneur, euse: adj.m.→ chalutier senneur: [漁]引き網漁船、n.m.=seineur. /tournée: n.f.[演劇・コンサートなどの行程が定まった職業上の] 巡業、ツアー、巡回; [2隻の船で引く] 引き網. /traille: n.f.渡し綱[渡し舟を渡すために対岸へ張った綱]; [川に渡した綱に舟を繋ぎ、渡し綱に沿って、水流を利用して進む] 繋留渡し舟、ロープ式渡し舟; フェリーロープ、フェリーケーブル; [漁]曳き網、トロール網、地引き網. /traîne: n.f.引きずること、引きずられること、曳くころ; [漁]曳き網、地引き網、引き縄; 綱巻き車; [海]曳航物; [雲の]たなびく尾. ・ pêche à la traîne: 引き縄漁、底引き網漁. /traîneau: n.m.(pl. -x)橇(そり); [漁][魚などを捕える]曳き網、大曳き網.
hikinawa引き縄: ligne de traîne.
/traîne: n.f.引きずること、引きずられること、曳くころ; [漁]曳き網、地引き網、引き縄; 綱巻き車; [海]曳航物; [雲の]たなびく尾. ・ pêche à la traîne: 引き縄漁、底引き網漁. /traîneau: n.m.(pl. -x)橇(そり); [漁][魚などを捕える]曳き網、大曳き網.
hitto[魚の]ヒット: 当たり. hogei-hou捕鯨砲: lance-harpon(adj.)→ canon lance-harpon: [漁]捕鯨砲.
houryuu放流: → empoissonnement: n.m.[魚の]放流、幼魚養殖、養魚.
・ empoissonner un étang de carpeaux: 池に鯉(こい)の稚魚を放流する・放す. /peupler: v.t.[ある地域・土地に]人を住まわせる、植民する; [養殖場・禁漁区などに]魚(鳥・獣)を放つ; [ある場所に]動物を増やす. ・ alevins qui peuplent cet étang: この池にたくさん棲息する稚魚. ・ peupler un étang d'alevins: 池に稚魚を放つ. /rempoissonner: v.t.[池などに]再び魚を放流する(ふやす)、新たに養魚する. ・ rempoissonnement: n.m.[池に]再び魚を増やすこと. ・ rempoissonner un étang: 再び池に魚を入れる. /repeuplement: n.m.[人・動物を]再び住みつかせること; [人口・動植物を]再び増やすこと. ・ repeuplement d'un étang: 池の魚の再増殖. /repeupler: v.t.再び人・動物を住みつかせる; 人口・動植物を再び増やす. ・ repeupler une rivière: 川に再び魚を放流する. ・ repeupler un étang d'alevins: 池に再び幼魚を放す.
/bordigue: n.f.[魚を捕るために(あるいは、保護するために)柵や網で作った、海辺の] 囲(かこ)い、魚囲い; 生け簀(いけす)、 生洲(いけす)、海水生け簀. /bourriche: n.f.[狩猟の獲物・魚介(魚・牡蠣(かき)など)などの運送用の]籠(かご); 籠一杯; [網の]生け簀(いけす). /boutique: n.f.[漁](a)いけす; (b)[漁][漁船の中に造られた; 船底の]いけす; 店; [既製服を売る]洋装店、ブティック. /cage: n.f.[漁]いけす; 簗(やな)(nasse)、筌(うえ); [動物飼育用の]檻(おり)、籠(かご)、鳥籠. /congre: n.m.[川の]生け簀(いけす)、生洲(いけす)(=congrier, congrois). /congrier, congrois: n.m.[川の]生け簀(いけす)、生洲(いけす)(=congre). /parc: n.m.[漁][海中の]生け簀(いけす); [漁][円形の]網囲い; [貝類の]養殖場、牡蠣(カキ)養殖場(=parc à huîtres); 塩田; [海]中部甲板; 自然公園、公園、遊園; 駐車場; 置場; [軍]廠(しょう). /parquer: v.t.[貝類、特に牡蠣(カキ)を]養殖場に入れる(→ parc); [牛・羊などの家畜を] 囲いの中に入れる、囲いに入れる. /parquer des huîtres: 牡蠣を養殖場に入れる. /pêcherie: n.f.漁場、漁区、漁業場; [方言][港の]魚貯蔵所; 生け簀(いけす). /ravoir: n.m.養殖いけす; 川網; [漁]立網. /réservoir: n.m.貯水池; 水槽、タンク; 養魚池; [魚を入れる]水槽; 生け簀(いけす)(vivier, aquarium); 釣り堀. /serre: n.f.室(むろ)、温室(=serre chaude); [漁][船中の]魚類貯蔵氷函; 生け簀(いけす)、養魚池; [海][古語]梁受材、 副梁(はり)受け材、接合剤、つなぎ. /stabulation: n.f.[魚などを]生簀(いけす)に入れること、いけす飼育; [牡蠣(かき)の]養殖所飼育. /stabuler: v.t.[魚などを]生簀(いけす)に入れる. /vivier: n.m.[魚・甲殻類の]養魚池; [漁船の]生け簀(す); 水槽付きの漁船、生け簀のある漁船.
ikie生き餌:
/s'enferrer: v.pr.[魚が自分から]針にかかる、餌に引っ掛かる、[魚が]釣り針を呑み込む. /locher: v.t.[漁][生き餌(え)を]釣り糸にくくりつける. /vif, vive: 生きている、生き生きしたn.m.生身(なまみ); [漁・釣]生餌(いきえ)、生き餌(え)、いきえさ. ・ pêcher au vif: 生き餌で釣る.
isaribi漁り火、漁火、いさり火: →
/pêche à feu pêche, pêche au feu: 漁り火(いさりび)による漁. /pêche au feu: かがり火をたいてする漁. /pharillon: n.m.小燈台; [漁][集魚灯を焚(た)く]鉄製のかご[船首に吊るす]、集魚燈を焚くかがり篭、 [漁][漁船の舳先(へさき)に吊るす]いさり火籠(かご); 漁火(いさりび); 集魚灯による漁(=pêche au pharillon)、いさり火漁 (=pêche au pharillon)、集魚燈を焚くかがり篭による漁獲、漁火を燃やして行う漁獲.
iseebi-ami伊勢蝦網、伊勢海老網、伊勢エビ網: →
/langouste: n.f.[動]伊勢蝦(イセエビ)、イセエビ[属]、ロブスター[海産; 食用エビ]; [俗語]ザリガニ. /langoustière: n.f.伊勢蝦網、イセエビ捕獲用の網. /langouste: n.f.[動]伊勢蝦(イセエビ)、イセエビ[属]、ロブスター[海産; 食用エビ]; [俗語]ザリガニ.
ito糸: → ligne flottante: [漁][浮子(うき)・浮きによる]宙づりの糸 [参考][釣]浮子・浮き: 釣り糸などにつけて
水面に浮かべる木片など [参考]flottant, e: adj.潮と共に流れる、[水に]浮かぶ、浮く、浮かんだ、浮いている、浮遊する、漂う;
[旗などが]翻る、風になびく、たなびく; 波立つ、逆巻き(さかまき)流れる; [経]浮動(変動)する、流動的な. itomaki糸巻き: → リール.
/drège, dreige: n.f.[漁]底引き網、曳網; 地引き網、地曳網. /gabare, gabarre: n.f.[海]川で大きな船の荷の積み降ろしをする船、大型川舟; [河川・港湾用の]運送船、艀(はしけ)、 伝馬船; [昔の海軍の]輸送船、貨物輸送船; [漁]地引き網; [大西洋沿岸の河口で用いられる]漁獲網; 大型曳き網(→ n.m.小型曳き網: gabaret); 漁船の一種. /hallope: n.m.[漁]地曳網. /seine: n.f.[漁]引き網(→ senne)、地曳網、地引網、地引き網. /seiner: v.t.[魚を]引網で取る、地引網で漁獲する、v.i.引網で漁をする、地引網で魚を取る、引網をかける. /seineur, euse: adj.地引をする、n.m.地引漁夫. /seyette: n.f.[漁]地引網. /traille: n.f.渡し綱[渡し舟を渡すために対岸へ張った綱]; [川に渡した綱に舟を繋ぎ、渡し綱に沿って、水流を利用して進む] 繋留渡し舟、ロープ式渡し舟; フェリーロープ、フェリーケーブル; [漁]曳き網、トロール網、地引き網. /traîne: n.f.引きずること、引きずられること、曳くころ; [漁]曳き網、地引き網、引き縄; 綱巻き車; [海]曳航物; [雲の]たなびく尾. ・ pêche à la traîne: 引き縄漁、底引き網漁.
kaeri返り: → あご.
kaeshibari返し針: → arrière-point: n.m.(pl. ~-~s)返し針. kagaribiかがり火: → 漁火、漁り火、いさり火.
kagibari鉤針: → angon: n.m.[甲殻類を捕る、返り付きの]やす、魚扠(やす)[カニ・エビなどを釣る]鉤針.
kago籠(かご): →
/gibecière: n.f.[漁夫の]魚袋、[釣り師・猟師などが肩に掛ける]獲物入れ. /gline: n.f.[釣り師の]びく、魚籠(びく). /manne: n.f.大型の柳籠; 魚籠. /torquette: n.f.[魚・鳥を運ぶ]籃(かご)、魚籠; 発送のために藁(わら)で包んだ鮮魚、籠入りの魚. kaiten回転: → hélice: n.f.螺旋(らせん); [海][船の]推進機、プロペラ、スクリュー [英語: propeller]; [飛行機の]プロペラ; 暗車、暗輪; [漁]回転鉤、回転針、スピンナー、回転ルアー.
kakiami掻き網:
・ pêcheur à la drague: すくい網の漁師. /draguer: v.t.[川・港などを]浚渫機(浚渫船)でさらえる、浚渫する; …に撈鎖(さぐり)を入れて捜す、撈錨で引き揚げる; [軍](draguer des mines)[機雷除去のために]掃海する、[機雷を]除去する; [漁]すくい網で採る; [漁][貝を] 桁網で採る; 掻き網ですくう; [海][錨が]水底を引きずる. /dragueur, se: adj.m.浚渫(掃海)する、浚渫の、n.m浚渫人夫; [漁]すくい網漁夫(漁師)、桁網漁夫、掻き網漁夫(=pêcheur à la drague); 浚渫船(=bateau ~); (~ de mines)掃海艇. /drainette: n.f.[漁]小さいすくい網.
kakimawasu掻き回す: → 水掻き.
kebari毛針(けばり):
/pêche à la moucheル: ルアー釣り、フライフィッシング. /pêcher à la mouche: 毛針(フライ)で釣る.
ketaami桁網(けたあみ):
・ pêcheur à la drague: すくい網の漁師. /draguer: v.t.[川・港などを]浚渫機(浚渫船)でさらえる、浚渫する; …に撈鎖(さぐり)を入れて捜す、撈錨で引き揚げる; [軍](draguer des mines)[機雷除去のために]掃海する、[機雷を]除去する; [漁]すくい網で採る; [漁][貝を] 桁網で採る; 掻き網ですくう; [海][錨が]水底を引きずる. /dragueur, se: adj.m.浚渫(掃海)する、浚渫の、n.m浚渫人夫; [漁]すくい網漁夫(漁師)、桁網漁夫、掻き網漁夫(=pêcheur à la drague); 浚渫船(=bateau ~); (~ de mines)掃海艇. /drainette: n.f.[漁]小さいすくい網.
kinchaku-ami巾着網: → bourse: n.f.[漁]袋形・袋状の網、巾着網(くんちゃくあみ); 財布、巾着(きんちゃく). kotei-duri固定釣り: → ligne dormante: [人が持っていなくてもよい]固定釣りの糸、固定底釣りの糸. kui[魚の]食い: → 当たり. kui杭: → palot: n.m.[魚網を張るための]杭(くい)、[漁用の]小さな杭、シャベル; [砂中の魚貝・虫を捕る] 細身のシャベル.
kuitsuku[魚などが]食いつく: [参照]食い、当たり.
/mordre: v.t.dir.(直接他動詞)噛む、かむ、咬みつく、かじる; [ネジなどが]食い込む、v.t.ind.(直接他動詞) (mordre à)[ …に]食いつく、v.i.咬みつく; [ …を]噛む、かじる; [餌(えさ)・誘惑などに]食いつく、引っかかる; [錨・ネジ・釘などが][ …に]食い込む; [歯車が]かみ合う. ・ Ça mord!: [話語][魚が]食っているぞ!、食いついた; ひっかかった. ・ Ça y est, un poisson mord.: やった。魚がかかったぞ. ・ mordre à l'appât: [魚が]餌に食いつく; [誘惑などに]引っかかる. ・ poisson qui mord: 釣れやすい魚. /toucher: v.t.dir.[ …に]触れる、さわる、接触する; 当たる、命中する; [船が]寄港する; [陸に]接近する. v.i.ind.[ …に(a` …)]触れる、さわる; [ …に(à …)]近づく、達する、届く; [船が]入港する. v.i.[海][船体が]水底(岩礁・突堤など)に触れる、擱座する; [船が]他船(水底・岸壁など)にぶつかる、接触事故を起こす [損害が軽微な場合 についていう]、衝突する; [釣りで魚が] 餌(えさ)に食いつく(触れる).
makiami巻き網: → glène: n.f.[海]巻き綱、捲綱、[巻いて重ねたロープの]輪. makidou巻胴(まきどう): → dévidoir: n.m.[綱・ホース・ケーブルなどの]巻き枠(まきわく)、巻き取り機、巻胴(まきどう)、 ドラム; [釣り糸の]リール; 紡ぎ機. makitoriki巻き取り機: → dévidoir: n.m.[綱・ホース・ケーブルなどの]巻き枠(まきわく)、巻き取り機、巻胴(まきどう)、 ドラム; [釣り糸の]リール; 紡ぎ機. michiito道糸、みち糸: → cordée: n.f.[漁][底延縄(cordeau)に付けらえた]みち糸; [漁]延縄; [ウナギの]釣り糸; [綱で縛ったものの]一締め. mimizuミミズ: → vermée: n.f.[漁][釣り糸につけられた] 餌(えさ)のミミズ、たくさんのミミズを糸に通した餌; それを用いる漁/vérotis: n.m.[漁][釣り餌に用いる]ミミズの類. mitsuryou密漁: → filetage: n.m.[網を用いての]密漁、密猟.
mizukaki水掻き: → bouille: n.f.[魚をひき寄せる(おびき出す)ために、水底を掻き回す]水掻き竿(ざお).
mori銛、もり:
/épée: n.f.剣; [漁]魚扠(やす)、漁叉; [網作りの]木釘. /épée de pêcheur: [漁]銛(もり)、やす[竹冠に措と書く]. /foène, foëne: n.f.[漁][魚捕り用の]簎(やす)、漁叉(もり)、銛(もり)、大銛、太い銛. /foéner, foëner: v.t.[魚を]やす・銛で突く. /fouine: n.f.簎(やす)、銛(もり)、[マグロなどを突く大型の]漁叉(やす)、突きん棒; [干し草などの積み上げ用の]三叉 フォーク、熊手. /fourche: n.f.熊手、[農業用]フォーク; [魚捕りの; 魚を刺す]簎(やす); [海][叉(また)になっている]船具. ・ fourche à deux dents: 二叉のやす(フォーク). ・ fourche à trois dents: 三叉のやす(フォーク). /fuscine: n.f.[古代ローマ][古代の漁夫が使った]三叉の銛(もり)[海神ネプトゥヌス(Neptune)の象徴]. /harpon: n.m.銛(もり)[特に捕鯨用]; [古語][敵船を接舷させるための]鉄鉤(てつかぎ)、引っ掛け錨. ・ fusil à harpon: 水中銃. ・ harpoire: n.f.銛(もり)綱. ・ harpoise: n.f.銛の先端. ・ lancer le harpon au canon: 捕鯨砲を撃つ. ・ pêche au harpon: 銛漁. /harponnage, harponnement: n.m.銛を撃ちこむこと(打ち込むこと)、銛で突くこと、銛を投げること. /harponner: v.t.[鯨などに]銛を撃ちこむ、銛を打ち込む、銛を投げる、銛で突く. /harponneur: n.m.銛の射手、銛打ち. /obus: n.m.砲弾; [漁]捕鯨銛(もり). /varre: n.f.[海亀を捕る(突く)]銛(もり)、漁叉(もり). /varrer: v.t.またはv.i.[亀を]銛で突く、漁叉(もり)で漁をする. /varreur: n.m.[海亀を捕える時の]銛を使う漁師・漁夫、[海亀の]漁叉(もり)漁夫.
/drifter: [英語]n.m.[海][海]流し網漁船. /filet flottant: 流し網 [参考]flottant, e: adj.潮と共に流れる、[水に]浮かぶ、浮く、浮かんだ、浮いている、浮遊する、漂う; [旗などが]翻る、風になびく、 たなびく; 波立つ、逆巻き(さかまき)流れる; [経]浮動(変動)する、流動的な. /roie: n.f.[漁]流し網.
nagashiduri流し釣り: pêche à la dérive.
nageduri投げ釣り:
/lancer: n.m.投げること、放つこと. /pêche au lancer: [漁]リール竿(canne à lancer)による投げ釣り、カスティング. /lanceur, se: n.投げる人; 投げ釣りをする人; 発起人、n.m.発射装置、ランチャー.
nigoraseru濁らせる:
nijuu-ami二重網: →
nijuu-bari二重針: → nishin-ryouニシン漁: → harengaison: n.f.ニシン漁; ニシン漁期/harenguière: n.f.ニシン網/ harengueux, harenguier: n.m.[漁]ニシン船; ニシン漁師/harenguier: n.m.ニシン船、ニシン漁船; ニシン漁師(漁夫)/ jardinet: n.m.小さな庭; [漁][漁船の]樽詰めニシンを置く場所. nomikomu呑み込む: → engamer: v.t.[漁][魚が]釣り針を呑み込む、v.i.[魚が]釣り針を呑(の)み込む.
omori錘、重り、おもり: →
/cendrée: n.f.石灰殻; [漁・猟][小さな獲物・魚獲り用の] 最小散弾; [漁][網・釣り糸の]おもり. /cliquette: n.f.[漁網につける] 錘(おもり)石、おもり. /lest: [オランダ語]n.m.sing.(=pl.なし)[海][船の]バラスト、脚荷(あしに)、底荷(そこに)[船に安定を与えるために船底に積む]; [漁][漁網の]錘(おもり)、おもし. /lesté(e): (lesterのp.p.)adj.[船などが]バラストを積んだ; [釣り糸などが]おもりのついた. /lester: v.t.[船・気球などに]底荷(バラスト)を積む・積み込む、底荷をつける; [漁網・釣り糸などに]錘(おもり)をつける、 おもしをつける. /plomb: n.m.鉛; [釣り糸・漁網などの]おもり、鉛玉; [海]測鉛(そくえん)、測深錐、測深錘(おもり)(=plomb de sonde); [電気]ヒューズ(fusible). ・ mettre trois plombs à sa ligne: 釣り糸に3つおもりを付ける. /plombée: n.f.[漁]おもり、鉛、錘(おもり)をつけた釣り糸・網. /plomber: v.t.[釣り糸などに]鉛のおもりをつける、鉛を付ける. ・ plomber un filet: 漁網に鉛のおもりを付ける.
otoriおとり: → leurre: n.m.[漁][魚の]作り餌; 香餌(こうじ)、わな; [釣りの]ルアー、擬餌鉤(ぎじばり); [狩]おとり.
/moulinet: n.m.[釣り用・釣り糸の; 釣竿に取り付ける]リール、絲車; [ウインチの]巻胴; 巻き上げ機(=moulinet d'un treuil)、 捲揚機械(ウインチ); 回転式流速計、測流計、[羽根車式]流速計; 回転式の機械(装置). /plioir: n.m.[釣り糸を巻き付ける]釣り糸巻き、[釣り糸などを巻き取る小さな板でできた]糸巻き. /tambour de moulinet: [釣り竿の]リールドラム. /touret: n.m.[釣り糸などの]糸巻き、釣魚用リール、[ウインチの]胴; [海][綱などの]巻枠; [海]=tolet([海]櫂座(かいざ)ピン、 トールピン)、櫂杭; [機]回転研磨機; ろくろ、小型旋盤.
rua-ルアー:
/leurre: n.m.[漁][魚の]作り餌; 香餌(こうじ)、わな. /leurre: n.m.[釣りの]ルアー、擬餌鉤(ぎじばり); [狩]おとり. /leurrer: (v.t.)[魚などを]おとり(作り餌)でおびき寄せる. /mouche: n.f.蝿(はえ)、ハエ; [釣り用の]毛針、毛鉤(けばり)、蚊鉤(かばり)、ルアー (=mouche artificielle)、フライ(=mouche artificielle[釣]蚊針); 斑点; (M~、Bateau M~)[セーヌ河を通う]川蒸汽、 川蒸汽船、乗合蒸汽船、遊覧船、観光船; [海軍]通報艦; [19世紀頃の]偵察艇、小型報知艦(=mouche d'escadre). ・ pêche à la moucheル: ルアー釣り、フライフィッシング. /poisson nageur: [漁]擬餌(ぎじ)、擬餌針、ルアー.
ryou漁(りょう): → 釣り.
/pêche à la sardine: イワシ漁. /pêche au(du) hareng: ニシン漁、鰊漁. /pêche au maquereau: 鯖漁. /pêche côtiére, petite pêche: 沿岸漁業、沿海漁業. /pêche des truites: マス漁. /pêche hauturière: 沖合漁業. /pêche lointaine: 遠洋漁業. /pêche maritime: 海洋漁業、海面漁業. /pêche miraculeuse: 奇跡の漁[ルカ伝から]; 非常に多い水揚げ. /petite pêche, pêche côtière: 沿海漁業、沿岸漁業. /pêcher la daurade: 鯛漁をする. /pêcheur, euse: n.漁師、漁夫、漁業者; [趣味での]釣り人、釣りの好きな人; [貝・海綿動物などの水産物の]採取者、 adj.漁をする、漁の、漁業の、漁業用の; 漁師の. /sardinier(ère): adj.イワシの、サーディンの; イワシ漁の; イワシ缶詰製造の、n.イワシ捕りの漁師(漁民)、イワシ漁師; イワシ缶詰[製造]工、 n.m.イワシ漁船(=bateau sardinier)、イワシ船; イワシ網、[イワシ漁で使う]網、巻き網、n.f.[昔の 甲板のない]小型イワシ漁船、イワシ漁用のボート. /terre-neuvas(pl. ~[s]-~), terre-neuvier(pl. ~-~[s]): adj.ニューファンドランド(Terre-Neuve)に鱈(たら)漁に行く、 [フューファンドランドまで出かけて]遠洋漁業をする、n.m.inv.ニュー・ファンドランドに鱈漁に行く漁船(漁夫)、 [フュー・ファンドランドまで出かけて]遠洋漁業をする漁船・漁夫.
sakatoge逆刺(さかとげ): → あご.
sadeami叉手網(さであみ): →
saishu[牡蛎などの]採取: déparquement(m).
/détroquer: v.t.[牡蠣(かき)の稚貝(ちがい)を]採苗する. /pêche au corail: サンゴの採取. /pêche des perles: 真珠の採取. /pêche aux oursins: ウニの採取. /pêcher des huîtres perlie`res: 真珠貝を採る. /pêcher des oursins: ウニを採る. /pêcher du corail: サンゴを採る. saku柵(さく): → grillage: n.m.[窓などの]格子、[特に]鉄格子; [窓などに張る]金網; 金網張りの柵; [池の魚が逃げるのを 防ぐために、池の流水口を塞ぐ]格子、網、柵(さく).
sao竿:
/bouiller: v.i.[漁][水掻き竿で]水底を掻き回す、v.t.[漁][水を]竿で濁らせる(→ brasser). /branlette: n.f.[3本つなぎの釣竿の]仲竿. /brin: n.m.[切り株から伸びた]若芽、若枝; [糸・わらなどの]切れ端; 麻(あさ)の長い繊維; [綱などの]単糸、[綱を撚る]細綱、紐; [滑車・動輪の]ロープ、ベルト; [漁][釣り竿の]継ぎ竿. ・ brin d'une canne à pêche: 継ぎ竿の各々の竿. /canne: n.f.[植]アシ(ヨシ)[の類]、葦(あし)・藤(とう)・竹などの大型イネ目植物の通称; 竿(さお); 杖、ステッキ. ・ canne à pêche: [魚釣り用]継ぎ竿、釣竿. /pêche à la ligne: [糸]釣り、竿釣り、手釣り. /pêcher à la ligne: [目的語なしに]竿釣りをする、手釣りをする、[糸]釣りをする. /pommeau: (pl. ~x)n.m.[釣竿の]もと. /saumier: n.m.[釣り針にかかったサケなどを陸や船に引き上げる時に用いる]魚かぎ、かぎ竿、サケを刺す叉(やす). /scion: n.m.新芽、若枝; [釣り竿の]竿先(さおさき)、穂先(ほさき). /tambour de moulinet: [釣り竿の]リールドラム. /tangon: n.m.[海]ブーム [大三角帆の裾(すそ)を張る帆桁]; [軍艦の]張り出し桁 [小船を繋ぎ、水雷よけの網を張る]、 [海][ボートを係留する]張り出し桁(けた)、ブーム、[海]係船桁 [小舟を係留するための横木で、船外に張り出される]; [舷へ登る ための梯をかける]張り出し桁; [カツオ・マグロ漁船の]張出し竿. ・ tangon de pêche: [引き網を船から隔てるために漁船に固定した] 竿. /virole: n.f.[つなぎ式の釣り竿の各先端にある] 受け輪.
sarukan転鐶(さるかん):
・ croc à émerillon: 回転フック、回りフック、転鐶付き鉤. /émerillonner: v.t.[さる鐶(かん)・さる環・転環を使って]索具をよじる.
sashiami刺し網: → manet: n.m.[漁]刺網(さしあみ)、刺し網/sanglon: n.m.[漁]刺し網
/tramail: n.m.[漁]三重刺網、三段刺網. sasoiduri誘い釣り: → pêche à la trembleuse: [漁][釣り糸を絶えず動かす]誘い釣り、釣り糸を絶えず動かす魚釣り法. sensui潜水: → chasse sous-marine: [水中銃などによる] 潜水漁、潜水魚突き/pêche sous-marine: 潜水漁法、スピアフィッシング (=chasse sous-marine). shaberuシャベル: → palot: n.m.[魚網を張るための]杭(くい)、[漁用の]小さな杭、シャベル; [砂中の魚貝・虫を捕る] 細身のシャベル. shibiami鮪網(しびあみ): → madrague: n.f.[漁][方言][地中海沿岸で用いられる、いくつかの升(ます)からなる] マグロ漁用の定置網、 鮪網(しびあみ)/thonaire: n.m.[漁][地中海で用いられる]マグロ網、鮪網(しびあみ). shuugyotou集魚灯: → pharillon: n.m.小燈台; [漁][集魚灯を焚(た)く]鉄製のかご[船首に吊るす]、集魚燈を焚くかがり篭、 [漁][漁船の舳先(へさき)に吊るす]いさり火籠(かご); 漁火(いさりび); 集魚灯による漁(=pêche au pharillon)、いさり火漁 (=pêche au pharillon)、集魚燈を焚くかがり篭による漁獲、漁火を燃やして行う漁獲. soko-duri底釣り: → cordeau: (pl.~x)n.m.細縄、小綱; 綱、[海]引き綱; [漁]底延縄(そこはえなわ)、[浮きがなく、 複数の針がついた]底釣りの糸. soko-haenawa底延縄: → cordeau: (pl.~x)n.m.細縄、小綱; 綱、[海]引き綱; [漁]底延縄(そこはえなわ)、[浮きがなく、 複数の針がついた]底釣りの糸/ligne de fond: 底延縄(そこはえなわ)、[浮きがなく、複数の針がついた]底釣りの糸 /traînée: n.f.細長く続く跡; [漁]底延縄(そこはえなわ)/vermille: n.f.[漁][ウナギ用の]底延縄(そこはえなわ)、ウナギ釣りの道具. suichuujuu水中銃: fusil sous-marin [参考]fusil: n.m.銃、小銃; 射撃手、射手、砲手.
sukui-amiすくい網: →
/pêcheur à la drague: すくい網の漁師. /draguer: v.t.[川・港などを]浚渫機(浚渫船)でさらえる、浚渫する; …に撈鎖(さぐり)を入れて捜す、撈錨で引き揚げる; [軍](draguer des mines)[機雷除去のために]掃海する、[機雷を]除去する; [漁]すくい網で採る; [漁][貝を] 桁網で採る; 掻き網ですくう; [海][錨が]水底を引きずる. /dragueur, se: adj.m.浚渫(掃海)する、浚渫の、n.m浚渫人夫; [漁]すくい網漁夫(漁師)、桁網漁夫、掻き網漁夫(=pêcheur à la drague); 浚渫船(=bateau ~); (~ de mines)掃海艇. /drainette: n.f.[漁]小さいすくい網. /truble: n.f.[漁]たも網、すくい網、さで網(→ trubleau)→ trubleau: (pl. ~x)n.m.[漁]小さいたも網、小たも網.
supinna-スピンナー: → hélice: n.f.螺旋(らせん); [海][船の]推進機、プロペラ、スクリュー [英語: propeller]; [飛行機の]プロペラ;
暗車、暗輪; [漁]回転鉤、回転針、スピンナー、回転ルアー. suso-ami[漁]裾網: souillardière(f).
tamo手網、たも: → たも網.
tamoamiたも網:
/pêchette: n.f.[方言][ザリガニ用の]たも網、ザリガニ漁業用の網、[蝦を捕るための]玉網. /treuille: n.f.[小エビを捕る]小型たも網. /truble: n.f.[漁]たも網、すくい網、さで網(→ trubleau). /trubleau: (pl. ~x)n.m.[漁]小さいたも網、小たも網(→ truble). tanshin単針: hameçon simple(→ 複針・ふくばり).
tara-ryouタラ漁: → morutier, moruyer: n.m.鱈漁船、鱈漁の船; 鱈漁夫、鱈漁の漁夫、adj.m. 鱈漁船(鱈漁夫)の、
鱈漁をする.
tateami立網:
/goulotte: n.f.[漁獲用の筌(うえ)・簗(やな)などの]開口部(→ goulet). /palot: n.m.[魚網を張るための]杭(くい)、[漁用の]小さな杭、シャベル; [砂中の魚貝・虫を捕る] 細身のシャベル. /ravoir: n.m.養殖いけす; 川網; [漁]立網. /venet: n.m.[漁][干潮時に魚が網に入るように、魚を導き入れる口を陸側に向けて張られた]張網、半円形建網、半円形定置網、 [干潮時を利用する]袋網. /verveux: n.m.[漁]漏斗(じょうご)型の網; [捕魚用の]立網(たてあみ). teduri手釣り: → pêche à la ligne: [糸]釣り、竿釣り、手釣り/pêcher à la ligne: [目的語なしに]竿釣りをする、手釣りをする、 [糸]釣りをする.
toro-ruトロール:
/chalut: n.m.[漁]曳網、トロール、トロール網、底引き網. ・ pêcher au chalut: トロール網漁をする. ・ pêcher la morue au chalut: タラ(鱈)をトロールで獲(と)る. /chalutage: n.m.[漁]曳網漁業、トロール漁業、底引き網漁業. /chaluter: v.i.曳網(トロール)漁業をする、曳網を曳く. /chalutier(ère): adj.曳網(トロール網)で行う、トロールの、曳網の、底引き網の、n.m.(chalutier)トロール漁夫、トロール漁従事者、 底引き網漁夫、曳網漁夫; トロール船、トロール漁船、曳網漁船. ・ chalutier à vapeur: トロール汽船. ・ pêche chalutière: .[漁]曳網漁業、トロール漁業、底引き網漁業(=chalutage). /gangui: n.m.[地中海の]トロール網[船](→ chalut). /pêche à la drague: トロール漁. /pêche à la grague: トロール漁業. /pêche au chalut: トロール漁業. /traille: n.f.渡し綱[渡し舟を渡すために対岸へ張った綱]; [川に渡した綱に舟を繋ぎ、渡し綱に沿って、水流を利用して進む] 繋留渡し舟、ロープ式渡し舟; フェリーロープ、フェリーケーブル; [漁]曳き網、トロール網、地引き網. /traîne: n.f.引きずること、引きずられること、曳くころ; [漁]曳き網、地引き網、引き縄; 綱巻き車; [海]曳航物; [雲の]たなびく尾. ・ pêche à la traîne: 引き縄漁、底引き網漁. /trôle: n.f.→ filet à la trôle: トロール網.
tegusu[釣]てぐす: crin de Florence [参考]crin: n.m.[特に馬の]たてがみの毛. teichi-ami定置網: → diable: n.m.悪魔; 奴、男; [漁][冬期のニシン漁などのための]定置網; [魚](diable de mer)アンコウ[エイ・ オニカサゴなどの通称名としても用いられる]; 大エイ.
toku[網目などを]解く:
/démailler: v.t.[海][鎖を]錨から取りはずす、[繋環を開いて鎖を]はずす、[鎖の]継ぎ目を解く; [海][錨・帆などに結びつけられて いたものの]継ぎ目を解く、解いてはずす; [網などの]網目を解く、網目をほつれさせる; 編み目を解く. ・ se démailler: v.pr.継ぎ目が解ける; 網目が解ける. /madrague: n.f.[漁][方言][地中海沿岸で用いられる、いくつかの升(ます)からなる] マグロ漁用の定置網、鮪網(しびあみ). /venet: n.m.[漁][干潮時に魚が網に入るように、魚を導き入れる口を陸側に向けて張られた]張網、半円形建網、半円形定置網、 [干潮時を利用する]袋網.
toami投網:
tsugizao継ぎ竿: → brin: n.m.[切り株から伸びた]若芽、若枝; [糸・わらなどの]切れ端; 麻(あさ)の長い繊維; [綱などの]単糸、[綱を撚る]細綱、紐;
[滑車・動輪の]ロープ、ベルト; [漁][釣り竿の]継ぎ竿.
tsukinbou突きん棒: → fouine: n.f.簎(やす)、銛(もり)、[マグロなどを突く大型の]漁叉(やす)、突きん棒; [干し草などの積み上げ用の]三叉
フォーク、熊手.
tsuri釣り:
/pêche: n.f.魚とり、魚釣り; [鯨・海豹(アザラシ)などの]捕獲; [真珠・珊瑚(さんご)・海藻などの]採取、引き揚げ; 釣り(=pêche à la ligne); 漁、漁業; [集合的]捕れた(獲れた・取れた)魚[類]、漁獲物(=produits de la pêche); 漁獲高; 釣果(ちょうか); 釣り場、釣場、漁場; [法]漁業権、漁獲権; [鯨などの]捕獲権(=droit de ~). ・ aller à la pêche: 釣りに行く. ・ faire [une] bonne pêche: 大漁である. ・ ouverture de la pêche: 釣りの解禁→ fermeture de la pêche: 漁期の終了. ・ pêche abondante: 豊漁. /pêcher: v.t.[魚を]とる(捕る・獲る・捕える)、釣る、漁する; [魚以外の、貝・サンゴ・海藻などの水産物を]採取する、水中から 採取する; [鯨などを]捕獲する; [カニなどを]捕える; [目的語なしで]釣りをする; 引き揚げる.
/Le saumon se pêche en automne.: サケは秋に獲れる、サケの漁期は秋である. /pêche à la ligne: [糸]釣り、竿釣り、手釣り. /pêche à la truite: マス釣り、鱒(ます)釣り. /pêcher du poisson: 魚を捕る(獲る)、魚を釣る. /pêcher en mer: 海釣りをする. /pêcher en rivière, pêcher dans une rivière: 川釣りをする. /pêcher en rivière: [目的語なしに]川釣りをする. /pêcher la truite: マスを釣る、鱒(ます)を釣る. /pêcher un étang: 池の水を干し上げて魚を捕る(獲る). /poisson qui se pêche au ver de terre: ミミズで釣る魚. /se pêcher: v.pr.釣られる、釣れる、漁される、捕れる、獲(と)れる、採れる. /repêchage: n.m.[魚を]再び釣り上げること; 水から引き上げること. /repêcher: v.t.[魚を]再び釣り上げる、再び漁をする; 水から引き上げる.
tsuribari釣り針:
/bricole: n.f.[漁]二重針、複針、[背中合わせの]二重釣り針; 船体の動揺; ぶっ込み針の釣り糸; 小間物; [話語]つまらない仕事、つまらないもの; [中世の]弩砲(どほう). /engamer: v.t.[漁][魚が]釣り針を呑み込む、v.i.[魚が]釣り針を呑(の)み込む. /épinette: n.f.[棘(とげ)で作った]釣り針、棘製の釣り針; [植]モミ(樅). /haim, hain: n.m.[方言][主にノルマンディで]釣り針; [海]鉤竿(かぎざお). /hameçon: n.m.釣り針. ・ hameçon simple: 単針. ・ hameçon à deux crochets: 二本ケンケン[引き釣り用]. ・ mettre l'appât à l'hameçon: 釣り針に餌をつける. ・ mordre à l'hameçon, prendre l'hameçon; gober l'hameçon: [魚が]釣り針にかかる、[魚が]針に食いつく、餌につく. /hameçonné, e: adj.(hameçonnerのp.p.)[魚が]釣られた、針にかかった; [釣り糸などが]釣り針のついている、釣り針のついた. /hameçonner: v.t.[釣り糸に]釣り針をつける、針をつける; [魚を]釣る、釣り上げる、針にかける. /hampe: n.f.旗竿; [釣り針の]軸. /hampette: n.m.[釣り針の]軸; [刷毛(はけ)などの]柄.
tsurigu釣り具:
/engins de pêche: 釣り道具、漁具 [参考]engin: n.m.道具、器具、機械; 武器、兵器; ロケット、ミサイル. /engins prohibés: 使用禁止の漁具・猟具. /acheter un equipement de pêche: 釣り用品を買いそろえる [参考]équipement: n.m.装備を施すこと; 装備、装具、用具一式、 着装、備品; 設備、施設; [海]艤装(ぎそう)、船具(ふなぐ); [釣・スポーツなどの]用具. /équipement de pêche: 釣り用具一式.
tsuriito釣り糸:
/gambe: n.f.[海]中檣索具の下端を支持する鉄鎖; (pl.で; bambes [de revers])[海]檣楼下静索(しょうろうしたせいさく)、 ハトックシュラウド; [漁][淡水魚用の]釣り糸. /libouret: n.m.[漁]鯖(さば)釣り糸 [多数の釣り針とおもりがつけられ、サバ釣りなどに用いる]. /ligne: n.f.(1)[紙などに引かれた] 線、ライン; (2)[分割・境界などの]線; (3)[バス・鉄道などの] 路線; 航路; (4)釣り糸; [糸のついた]釣り竿(=ligne de pêche)、釣り竿一式; (5)電線; 電話線; [海][特に先端に器具のついた] 綱; [軍]戦列、戦線; 赤道(=ligne équinoxiale). ・ ligne de fond: 底延縄(そこはえなわ)、[浮きがなく、複数の針がついた]底釣りの糸. ・ ligne de pêche: 釣り糸. ・ ligne de traîne: 引縄. ・ ligne dormante: [人が持っていなくてもよい]固定釣りの糸、固定底釣りの糸. ・ ligne flottante: 浮縄(うきなわ)、[浮きのついた]流し釣りの糸. ・ pêche à la ligne: 魚釣り. ・ pêcher à la ligne: 釣りをする. /locher: v.t.[漁][生き餌(え)を]釣り糸にくくりつける. /palancre, palangre: n.f.[漁]延縄(はえなわ)、浮き延縄、[釣り糸の一種]トロール釣り糸. /perruque: n.f.[釣・漁][釣り糸の]もつれ、もつれた釣り糸; かつら. /vrillage: n.m.[海]釣り糸のきず. tsurizao釣竿: → 竿.
/cage: n.f.[漁]いけす; 簗(やな)(nasse)、筌(うえ); [動物飼育用の]檻(おり)、籠(かご)、鳥籠. /goulet: n.m.[海]港・湾の狭い入り口、狭い(狭くなった)湾口(港口); [海]海峡、水道; 峡谷; [漁]立網(たてあみ)の円錐形の口、 [漁獲用の筌(うえ)・簗(やな)などの]開口部(→ goulotte). /goulotte: n.f.[漁獲用の筌(うえ)・簗(やな)などの]開口部(→ goulet). /nasse: n.f.[鰻・蝦(えび)・魚などを捕えるための] やな(簗)、魚梁(やな)、うけ(筌)、うえ(筌) [細く割った竹を円筒形 に編んでつくられた籠のような道具で水中に沈めて魚などを捕獲する]; [貝]ムシロガイ[類] [ムシロガイ科の貝の総称; 腐肉食性の 巻き貝]. ・ poser une nasse dans la rivière: 川に梁を仕掛ける. /nassone: n.f.エビ捕り魚梁(やな) . /panier: n.m.[漁][エビ・カニなどを捕えるための]筌(うえ)、梁(やな); [一般に、柄(え)のついた]かご、 ざる、バスケット; 一かごの分量、籠一杯分. /tambour: n.m.太鼓; 鼓手; [機]ドラム、胴、円筒、円筒形部、シリンダー; [網捲き用の]捲胴; [船]外車覆筐; [魚]ニベ[の一種] [鰾(うきぶくろ)で太鼓のような音を出す]; [漁][円筒状の]筌(うえ)、筌簗(うえやな)、梁簀. uinchiウインチ: → treuil: n.m.ウインチ、巻き上げ機、捲き揚げ機/treuil à bras: 手動ウインチ/ vindas, vindau(pl. -x): n.m.ウインチ、巻き上げ機. uke筌(うけ): → 筌(うえ).
uki浮き:
/flotteur: n.m.[漁][釣り糸・漁網などの]浮き、浮子(うき); [水上飛行機の]浮舟、フロート、[救命ボートの]フロート; 浮標、ブイ; [海]錨(いかり)浮標; 浮体、水に浮く物; [生][魚などの]浮き袋; [植][藻などの浮葉植物の]気泡体; 浮球、 フロート. /galet: n.m.[海岸・海浜・川原・川辺の]小さい玉石、丸い小石、石ころ、砂利; (plage à galets, plage de galets)砂利浜(じゃりはま); 小型滑車; [漁][魚網の; 網につける]浮子(うき). /liège: n.m.[漁]浮き; 浮標; コルク(→ liéger, lignage). /liégé(e): adj.[liégerのp.p.][漁][網・釣り糸などが]コルクの浮きを付けた、コルクを付けた(→ liéger, liège, lignage). ・ ligne liégée: コルクの浮きをつけた釣り糸. /liéger: v.t.[網・釣り糸などに]コルクの浮きを付ける(→ liège, lignage); コルクを塡める; 浮標をつける. /lignage: n.m.[漁][複数の釣り糸を支える]浮き(→ liéger, liège)、釣り糸の浮き. /pistillon: n.m.[釣り][道糸を浮かせるための]糸浮き. /postillon: n.m.[釣りで道糸を浮かせるための] 糸浮き、[釣り魚用の]浮標(うき)の一種. ukinawa浮縄: → ligne flottante: 浮縄(うきなわ)、[浮きのついた]流し釣りの糸.
uokagi魚鉤:
/baro: n.f.[ピレネ山の急流の]鮭捕り簗簀(やな). /bergat: n.m.ウナギ捕りの簗(やな). /bosselle: n.f.[漁]鰻(ウナギ)を捕る一種の簗(やな)、ウナギを捕る籠. /cage: n.f.[漁]いけす; 簗(やな)(nasse)、筌(うえ); [動物飼育用の]檻(おり)、籠(かご)、鳥籠. /gord: n.m.[漁][杭にかける]張網、簗(やな); 川に2列の杭を並べてその端に袋網をかけた漁場; 捕魚堰. /goulet: n.m.[海]港・湾の狭い入り口、狭い(狭くなった)湾口(港口); [海]海峡、水道; 峡谷; [漁]立網(たてあみ)の円錐形の口、 [漁獲用の筌(うえ)・簗(やな)などの]開口部(→ goulotte). /goulotte: n.f.[漁獲用の筌(うえ)・簗(やな)などの]開口部(→ goulet). /nasse: n.f.[鰻・蝦(えび)・魚などを捕えるための] やな(簗)、魚梁(やな)、うけ(筌)、うえ(筌) [細く割った竹を円筒形 に編んでつくられた籠のような道具で水中に沈めて魚などを捕獲する]; [貝]ムシロガイ[類] [ムシロガイ科の貝の総称; 腐肉食性の 巻き貝]. ・ poser une nasse dans la rivière: 川に梁を仕掛ける. /nassone: n.f.エビ捕り魚梁(やな) . /panier: n.m.[漁][エビ・カニなどを捕えるための]筌(うえ)、梁(やな); [一般に、柄(え)のついた]かご、 ざる、バスケット; 一かごの分量、籠一杯分. /tambour: n.m.太鼓; 鼓手; [機]ドラム、胴、円筒、円筒形部、シリンダー; [網捲き用の]捲胴; [船]外車覆筐; [魚]ニベ[の一種] [鰾(うきぶくろ)で太鼓のような音を出す]; [漁][円筒状の]筌(うえ)、筌簗(うえやな)、梁簀.
yasuやす:
/darder: v.t.やすで突く、投槍で突く; 射る、刺す; [漁][鯨に]銛を射込む、銛を打つ. /digon: n.m.[海][帆架につける]旗竿(はたざお); [漁][浅海の魚を突き刺して獲る]簎(やす)、[銛の]鉄鉤. /épée: n.f.剣; [漁]魚扠(やす)、漁叉; [網作りの]木釘. /épée de pêcheur: [漁]銛(もり)、やす[竹冠に措と書く]. /foène, foëne: n.f.[漁][魚捕り用の]簎(やす)、漁叉(もり)、銛(もり)、大銛、太い銛. /foéner, foëner: v.t.[魚を]やす・銛で突く. /fouine: n.f.簎(やす)、銛(もり)、[マグロなどを突く大型の]漁叉(やす)、突きん棒; [干し草などの積み上げ用の]三叉 フォーク、熊手. /foule: n.f.→ pêche à la foule: [漁]干潮時の砂底・泥底を踏んで(つついて)魚を追い出し、一種のやす (竹冠に措と書く)で刺して捕る漁法. /fourche: n.f.熊手、[農業用]フォーク; [魚捕りの; 魚を刺す]簎(やす); [海][叉(また)になっている]船具. ・ fourche à deux dents: 二叉のやす(フォーク). ・ fourche à trois dents: 三叉のやす(フォーク). /fuscine: n.f.[古代ローマ][古代の漁夫が使った]三叉の銛(もり)[海神ネプトゥヌス(Neptune)の象徴]. /gaffe: n.f.[海]爪竿(つめざお)、鉤竿(かぎざお)、フック、ガーフ; [漁]大きい釣魚を陸(おか)に上げる魚鉤(かぎ)、 [魚を水から上げる]ギャフ、魚鉤; [漁]魚叉(やす). /gaffeau: n.m.(pl.~x)[漁]小さい魚鉤; 小爪竿; [漁]魚叉(やす). /gaffer: v.t.[海][浮遊物などを]爪竿で引っ掛ける; [漁][魚を]魚鉤(ギャフ)で引き上げる、[舟・ボート・魚などを 鉤竿(かぎざお)(フック)で]引き上げる、引っ掛ける、[漁]魚叉(やす)で突く; [ボート漕ぎが]漕ぎそこねてひっくり返える. /lance: n.f.槍(やり); [銛(もり)にかかった鯨を突いて殺すための]やす(簎); [海](lance de sonde)測鉛、測鉛の先端部 [水深測量・底質探査のために用いる細長い鉛のおもり]. /saumier: n.m.[釣り針にかかったサケなどを陸や船に引き上げる時に用いる]魚かぎ、かぎ竿、サケを刺す叉(やす). /trident: n.m.三叉のフォーク; [神話][海神Neptuneの標票・象徴たる]3叉の戟(ほこ); [漁][3叉の]魚扠(やす) [魚を突き刺す道具].
yoriba[魚の]寄り場:
yotsude-ami四つ手網(よつであみ):
/ablier: n.m.四つ手網(よつであみ)、すくい網[角型で、長い柄付きの網; 小魚用](=ableret). /carré, e: adj.正方形の、四角い、四角な; 角ばった; 平方の、自乗の、n.m.[漁]四手網(よつであみ)、四つ手網(よつであみ) (→ carreau, carrelet)[漁網の一種]; 方帆船; [海]食事などに集まる部屋; [海](carré des officiers)[高級船員の]食堂、将校食堂、 士官食堂; [海]高級船員室、[海][軍艦の]士官室. /carreau: (pl. ~x)n.m.[海]最上後甲板の腰板; 四手網、四つ手網(→ carré, carrelet); 窓ガラス; タイル. /carrelet: n.m.[漁][小魚を獲るための]四つ手網、四手網(carré, carreau); [魚]カレイ、鰈(かれい)[類](plie)、カレイの一種; [魚]ヒラメ; 四角定規.
yougyo養魚:
/empoissonner: v.t.[池・川などに]魚を棲(す)ませる、魚・雑魚(ざこ)を放流する、幼魚を養殖する、魚を繁殖させる、魚の養殖をする. ・ empoissonner un étang de carpeaux: 池に鯉(こい)の稚魚を放流する・放す. /rempoissonner: v.t.[池などに]再び魚を放流する(ふやす)、新たに養魚する. ・ rempoissonnement: n.m.[池に]再び魚を増やすこと. ・ rempoissonner un étang: 再び池に魚を入れる. yowaraseru[魚などを]弱らせる: → fatiguer: v.t.疲れさせる; [釣][魚を]釣り上げる前に流して弱らせる・疲れさせる、 v.i.[船・機械などが]荷重(かじゅう)・張力などにやっと耐える、あえぐ、きしむ.
|
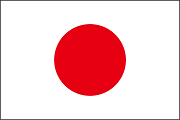
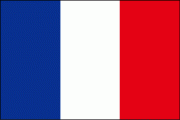
和仏/分野別 海洋辞典
漁具漁法用語
仏和/和仏
|
海洋辞典 |
海洋辞典 |
 Back to:
Back to: